-
交渉における協力志向・競争志向
2024年10月21日交渉における基本スタンスには、交渉相手と協力しあって目的を達成しようとする「協力志向」と、相手との勝負と考えてできるだけ得をしようとする「競争志向」があります。
私の交渉術の本を読んでいただいた方は、私が基本的には「協力志向」であることをご理解いただいていると思います。
では、果たして「協力志向」と「競争志向」では、どちらが優秀なネゴシエーターになれるのでしょうか。
アメリカの2つの大都市で弁護士を対象にした研究によると、同僚から「できるネゴシエーター」と評価されている弁護士のうち、75%が「協力志向」だったそうです。
また、イギリスの研究では、会社の労使交渉の担当者49人について実際の交渉の場における言動を調査したところ、特に優秀な人たちのほとんどが、「協力志向」だったそうです。
この結果だけを見ると、一般的には、「協力志向」の方が、優秀なネゴシエーターになりそうです。
しかし、アメリカ元大統領のトランプ氏は、「競争志向」に見えます。
「●●をしろ。さもなくば●●をするぞ!」というような脅し型の交渉スタイルのようです。
それでも不動産王になるくらいですから、交渉でも結果を出してきたのではないか、と推測します。
つまり、このような研究結果があっても、交渉は、人間対人間が行うものなので、その時その時で有効な方法が違うものですし、何より、自分に合った交渉スタイルかどうかがとても重要です。
自分が協調型なのに、無理に競争志向の交渉スタイルをとってもうまくいくはずがありません。
まずは、自分に合った交渉スタイルは、どのようなものなのか、それを決めること、そして、その後にその交渉スタイルでの交渉力をつけていくこと、が大切だと思います。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
韓非子の説得術
2024年10月14日他人を説得するのは、なぜ、こんなにも難しいのでしょうか。
どこが難しいのでしょうか。
それは、「韓非子」が教えてくれます。
韓非(韓非子)は、中国戦国時代の法家思想を代表する思想家です。
その中に、君主を説得する難しさについて説いた箇所があります(説難篇)。
韓非子は、説得のいくつかの要素を挙げます。
・説得する内容に関する知識を十分に持っていること。
・自分の考えをはっきり伝えるまで話すこと。
・自分の考えを自由自在に伝える弁舌。
しかし、これらは、全て難しいことではない、と断じます。
韓非子は、説得において、最も難しいのは、
・相手の心を読み取って、
・自分の言葉を相手の心に合わせて話すこと
ができるかどうか、だと言います。
そして、次の例を挙げます。
人は利益を求めるものであるから、相手に大きな利益が得られると説得するとします。
ところが、相手が名誉を強く求める人である場合、自分のことを下品で俗物扱いされた、と感じ、説得に応じないであろう、と言います。
この場合は、説得に応じた方が、大きな名誉を得られる、という方向で説得しなければならないわけです。
私の交渉術に関する本を読んでいただいた方であれば、この考えに同意するでしょう。
私も同意します。
そして、相手がどんな価値観を重視するかを見極め、その価値観に合わせた説得方法をとる方法について、1冊書いています。
興味があれば、ご一読をお願いいたします。
「7タイプ別交渉術」(秀和システム)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CRD41GK/
口コミレビュー(4.1)です。メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
心理的リアクタンスにご注意を。
2024年10月07日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
若いロミオとジュリエットは、出会うなり恋に落ちます。
しかし、周囲は猛反対。
反対されればされるほど、二人はより強く惹かれ合うことになります。
周囲は、二人を別れさせようと説得行動を取っているわけですが、これが逆効果になっているわけです。
心理学の概念に、「心理的リアクタンス」というものがあります。
これは、人が自由に行動できる権利や選択肢が制限されたり、脅かされたりしたときに、それに対して反発し、反対の行動や選択肢を強く求める心理的な反応のことをいいます。
私達は、他人を説得しようとする時に、概して、この心理的リアクタンスに反した行動を取ろうとします。
自分のため、あるいは相手のことを思って説得しようとする時、自分の考えを相手に押し付けようとするのです。
ロミオとジュリエットの周囲の人たちもしかり。
親は、子供が幸せに生きられるように、よく勉強して良い大学に入り、よい就職ができるようにと願って、「勉強しろ」と説得します。
しかし、子供の側は、そう言われた途端、やる気がなくなって、むしろ反抗して勉強をしないという選択を取りたがります。
では、どうすればいいか、ということですが、相手が自分で考えて決定した、というプロセスを作り出すことです。
そのためには、やはり質問が効果的ということになります。
質問は押し付けではありません。
人は、質問されると、そのことについて考え、答えを出そうとする性質を持っているからです。
しかし、ただ質問すればいい、というわけではありません。
たとえば、子供の対して、「宿題はやったの?」と質問するのは、子供に考えさせて答えを出させようとしているのではなく、「宿題はやったの?(やってないなら、さっさとやりなさいよ)」と、やはり自分の考えを押し付けているに過ぎないためです。
では、どのように質問すればよいのでしょうか。
次の本が、そのヒントになるでしょう。
Amazonでレビュー星4.5です。
「人生を変える「質問力」の教え」
https://www.amazon.co.jp/dp/B07V4PW8FP/メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
波平のパラドックス
2024年09月23日頭に髪の毛が1本もない人のことを、一般的に「ハゲ」といいます。
では、「サザエさん」の波平は、どうでしょうか。
髪の毛が1本ありますが、やはりハゲでしょう。
では、波平の兄の海平は、どうでしょうか。
髪の毛が1本増えて2本ありますが、やはりハゲでしょう。
では、もう1本足して3人になったらどうか、というのを繰り返していくと、最終的には髪の毛がふさふさになってもハゲになってしまいます。
しかし、そうすると、はじめの「頭に髪の毛が1本もない人のことを、一般的に「ハゲ」という」という前提と矛盾することになってしまいます。
これを、「波平のパラドックス」といいます。(元は、古代ギリシャの哲学者エウブリデスによる「ハゲ頭のパラドックス」です。)
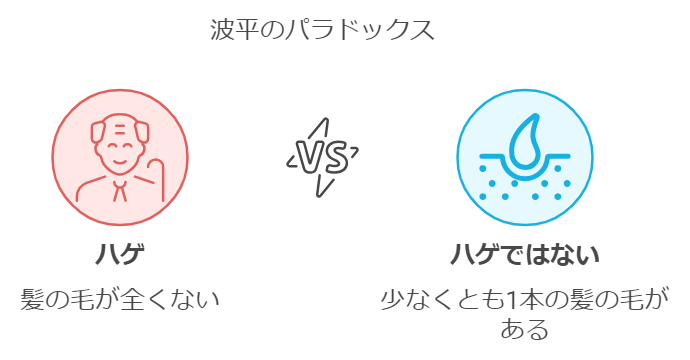
世の中には、このように境界が曖昧な言葉が溢れています。
議論する際に、言葉の定義を明確にせず、「斬新な」「骨太」「古い」「大きな」など、人によって解釈の異なる用語を前提にしていると、議論がちぐはぐになってしまう可能性があります。
たとえば、仏像を造る計画をたてる時、田中さんが、「大きな仏像」を2メートルの仏像と考えて議論し、山本さんが「大きな仏像」を20メートルの仏像と考えて議論していたら、設置する場所、材料、予算など、全く噛み合わないものとなります。
筋トレもしかりです。よくあるのが、「自重トレーニングで筋肉がつくか」という激しい議論です。
ある人は「自重トレで筋肉はつく」と主張し、ある人は「自重トレでは筋肉はつかない」と主張します。
SNSでも活発に議論されます。
しかし、この議論も前提が不明確なため、噛み合いません。
「筋肉がつく」という到達地点が、「細マッチョの筋肉」「体操選手のような筋肉」「ボディビルダーのような筋肉」のどれであるかによって、全く違った議論になるためです。
私たちは、日常的に他人と議論をしていますが、「なんか噛み合わないな」とか「どうしてこの人は理解してくれないのだろう。簡単な議論なのに。」と感じた時は、お互いの議論の前提が異なっていないかどうか、確認するのがよいでしょう。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
ストレスに対処する
2024年09月20日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
あなたは、普段、イライラしてストレスがたまっていませんか?
「仕事で帰り際に上司から急ぎの仕事を頼まれる」
「夫婦間で家事の分担が不公平だ」
「子供が勉強しない」
「恋人・友人にメッセージを送っても返信がない」ストレスがたまると、病気のリスクが高まり、不安やうつに繋がりやすくなり、集中力が低下し、睡眠障害の可能性が高まるなど、多くの弊害があります。
そこで、今回は、ストレスを低下させる簡単な方法をご紹介したいと思います。
1 深呼吸
その場ですぐに行えるストレス対策は、深呼吸です。
アメリカのペンシルベニア大学の研究で、テスト期間中の学生のストレスを減らす対策を調べたところ、ポジティブシンキングやタイムマネジメントなどを抑え、「深呼吸」が堂々の1位となったそうです。
ストレスを感じると、人間の呼吸は早く浅くなります。
そこで、深呼吸により、その自然の状況に介入することで、認知的不協和解消理論により、身体の状態に心の状態を一致させるという手法です。
2 自然音を聴く
次に受動的な方法として、スマホで自然の波の音、川の音、森の音などをすぐに聴けるように準備しておき、ストレスを感じたら、すぐに自然音を聴く、という方法があります。
イギリスのサセックス大学の実験で、学生に「自然音」「人工音(車の音など)」を聴かせた上で、ストレス度をチェックしたところ、自然音を聴いた学生は、副交感神経が活性化してリラクゼーション反応が大きかったそうです。
3 エクスプレッシブ・ライティング
最後は能動的な方法で、意志力が必要となります。
ストレスを感じたら、その時の感情や思考を包み隠さず書き記す、というものです。
これまでに多くの研究があり、不安やストレスへの効果が広く認められている、ということです。
心配や不安は、常に頭から離れないものですが、ストレスの素を書き出すことで、いったん心配事を棚卸しすることができ、そこから離れることができるということです。
ここで、他人に対する愚痴などの場合、ブログやSNSに書き出すことは、私個人としてはおすすめしません。
なぜなら、ブログやSNSは他人に開示され、他人に対し、ネガティブな影響を与えるためです。
スマホのメモなど、自分だけが見ることのできる媒体に書き出すことをおすすめしたいと思います。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
他人の失敗で快感
2024年09月09日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
「人生がうまくいく脳の使い方」(中野 信子 (著), ユカクマ (イラスト))の中に、面白い実験結果が書いてありました。
他人の不幸に対する反応で男女差があるかどうか、というものです。
「公正だと思う人」が苦しんでいるのを見た時は、男女ともに共感や痛みを感じる前帯状皮質が反応したそうです。
しかし、「公正でないと思う人」が苦しんいるのを見た時には、女性は同じく帯状皮質が反応したにもかかわらず、男性は、脳の快感と関連する腹側線条体が反応したそうです。
女性の方が共感力が高い、という結果は納得ですね。
男性の場合は、公正でない人が苦しむのは、当然の報いだ、との感情が強いのかもしれません。
あるいは、猿の時代のように、他人を蹴落としでも自分を地位を確保しようとする本能が残っているのでしょうか。
次に、これは男女ともの実験ですが、反対に、他人(実験では同窓生)が成功しているのを見ると、不安や痛み、不快を感じるそうです。
これは普段から経験しています。
成功した同窓生と自分を比較して、自尊心が傷つくからですね。
そして、その成功した同窓生が不幸に陥った場合には、快感の領域である腹側線条体が反応したそうです。
私たちは、なんと罪深い脳を持っているのでしょうか。
人格を成熟させ、この脳をコントロールする境地に到達したいものです。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
予定の実行率を上げる方法
2024年09月02日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
あなたは、特定の日に
「レポートをやろう」
「レジュメを作ろう」
「論文を読もう」
「部屋の掃除をしよう」など、ある行動をとろうと思っていたのに、つい忘れたり、惰性ですごしてしまってやらなかったり、という経験はありませんか?
今回は、このような場合に、実行しやすくする方法をご紹介します。
ドイツの社会心理学者ゴルヴィッツァー氏の実験です。
クリスマス休暇直前の学生たちを2つのグループに分け、「クリスマス休暇をどう過ごしたのか、というエッセイを書いてほしい」と依頼をしました。
締切はクリスマス当日から48時間以内です。
そして、1つのグループだけに、
エッセイを書く「時間と場所」を紙に書いてもらうという作業をしてもらいました。
その結果、
Aグループのエッセイ回収率は、32%。
Bグループのエッセイ回収率は、71%。
という結果が出ました。
その差2倍以上です。
これは、「実行意図」といいます。
実行意図とは、目標の実現へ向けて「いつ」「どこで」「どのように」するのかを明らかにすることです。
それだけで、実行率が2倍以上に向上するということです。
したがって、ある行動の実行率を上げたければ、その行動を「いつ、どこで、どのように」行うのかを具体的に、ありありとイメージすることです。
私が常々提唱している、習慣化するには、毎日必ず行う行動に結びつけること、もこの理論から説明することができます。
毎日ストレッチをすることを習慣化するには、歯磨きの後にストレッチすることをイメージし、決意することです。
そうすると、「朝、家で、歯磨きをした後で」ストレッチをするという実行意図を明らかにすることができます。
参考にしてください。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
メンタルローテーションとは?
2024年08月12日メンタルローテーションタスクというものがあります。
メンタルローテーションとは、心の中に思い浮かべたイメージを回転変換する認知的機能のことです。
そして、メンタルローテーションタスクとは、たとえば、ひとつの図形(たとえば、三角形)が示されて、それと同じ形のものを羅列された5、6個の図形の中から選ぶ、というものです。
同じ図形かどうかを判断するには、頭の中で図形を回転させなければなりません。
このメンタルローテーションタスクをアメリカのエリート大学生にやってもらう、という実験が行われました。
一般的には、男性の方が、女性より、早く正確に回答できるとされています。
そこで、実験では、タスクを行う前に、アンケートを実施しました。
アンケートで男女の性別の質問をされた場合、女子学生の正答率は男子学生の64%でした。
ところが、アンケートで自分の所属大学を質問された場合、正答率は男子学生の86%まで上がったということです。
この実験結果から、どんなことがわかるでしょうか。
プラスの自己イメージを持つことにより、能力がアップする、あるいは、マイナスの自己イメージを持つことにより、能力がダウンする、という仮説が成り立ちます。
ですから、試験の前、プレゼンの前、交渉の前、試合の前などには、強力に自己イメージをアップさせると、いつも以上の実力を発揮できる可能性がある、ということです。
ポジティブ思考をし、自信を持つには、どうしたらいいかについては、これまで何度もこのメルマガで書いてきましたので、今回は割愛します。
自分に自信を持って進んでいきましょう。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
怠惰を賛美する
2024年08月05日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
世の中には、勤勉は美徳であり、怠惰は悪いことだ、という価値観を持った人が多数います。
私は勤勉を美徳とは考えていませんが、怠惰に過ごしたくないと考えています。
なぜなら、怠惰は記帳な時間を浪費することだからです。
ところが、中には、怠惰を賛美する人もいます。
「『怠惰』なんて存在しない」(デヴォン・プライス著、佐々木寛子 翻訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)では、怠惰に過ごすことを推奨しています。
もちろん、働かずにすっと怠惰に過ごせ、と言っているわけではありません。
勤勉に働くことや生産性の高さで人の価値を測るという価値観のせいで、馬車馬のように働き、心身に異常をきたした例を多数挙げて、このような価値観が間違っている、と説いています。
休むことに罪悪感を感じることが間違いであると指摘します。
このタイトルだけを見ると、私も拒否反応を起こしそうですが、内容を読むと、至極まっとうなことが書いてあります。
休んだ方が生産性が向上することなどが書かれており、これは怠惰という言葉の印象とはかけ離れているように思います。
ノーベル文学賞を受賞したバートランド・ラッセルも、「怠惰への讃歌」という本を書いており、その中で、労働を人生の最終目的のように考えるのは間違っている、と言っています。
そして、なぜ労働が賛美されるのかというと、富裕層が貧民に不満を抱かせないために労働の美徳の価値観を植え付けたことなどが理由だといいます。
そして、奴隷制がなくなった時代には、1日4時間労働すればいいのだと主張しています。
なるほど。1日4時間働くだけであれば、残りの時間を好きに過ごせますね。
では、私はどうするか。
1日4時間弁護士業務を行い、残りの時間は、弁護士業務の質を高めるための勉強をし、本を書き(既に50冊以上書いています)、講演をして回るでしょう。
つまり、自分の時間を何に使うかというのは、自分の価値観によるのであり、勤勉がいいとか、怠惰がいいとか、そういう問題ではないと考える次第です。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
人を見抜く8つの方法
2024年07月29日こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
中国の兵法書の古典に、「六韜(りくとう)・三略」というものがあります。
この中に、相手を見抜くための「選将」という箇所があります。
これは、8つの方法からなっており、この8つの方法を試してみれば、その人がどんな人間であり、どれだけの能力をもっているかどうかがたちどころに判明するというものです。
8つの方法とは次のとおりです。
1 言葉で質問し、その答え方や回答の内容を観察する。
2 矢継ぎ早に質問を浴びせて、その反応と変化を観察する。
3 間者を使って裏切りを誘い、誠意のほどを観察する。
4 表だって質問し、その人柄を観察する。
5 金銭を扱わせて、その廉潔さを観察する。
6 異性を近づけ、その貞潔さを観察する。
7 困難な仕事を与えてみて、その勇気のほどを観察する。
8 酒を飲ませて酔わせ、その酔態を観察する。
8つの方法のうち、
1、2、4は、質問により相手を見抜く方法です。
やはり、相手を知るには、相手に質問するのが有効だ、ということです。
ただ、漫然と質問をしていても、相手を見抜くことは簡単ではありません。
「あなたは、カレーが好きですか?」
と質問しても、相手のことはわからないわけです。
カレーのことを聞くより、「これからの人生、挑戦と安定の2つの道があるとしたら、どちらを選びますか?」のような自分が重視する価値観に迫っていくような質問の方が相手のことを知るきっかけとなります。
「3 間者を使って裏切りを誘い、誠意のほどを観察する。」
「6 異性を近づけ、その貞潔さを観察する。」これは、普通に生活を送っている場合には、使うことはなさそうです。
「2 矢継ぎ早に質問を浴びせて、その反応と変化を観察する。」
これは、相手を追及しているような場面では有効ですが、日常生活で頻繁に使うと相手にストレスを与え、人間関係によくないようです。
「8 酒を飲ませて酔わせ、その酔態を観察する。」
これは、多くの人が日常的に活用していますね。
酒に酔うと、その人の本性が顔をのぞかせます。
私も十分気をつけたいと思います。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169

















