-
エッセンシャル思考の自動化
2021年10月18日メルマガより
今回のYouTube動画は、
【エッセンシャル思考を自動化】3ステップで重要なことだけに集中できる。10万部著者が解説。
エッセンシャル思考が重要なことはわかります。
しかし、常に重要なことを自分の意志で選択するのは大変です。
自動化してしまいましょう。
動画で解説しました。
ぜひ、ご覧ください。
さて、
これまで3回にわたり、エッセンシャル思考を解説してきました。
エッセンシャル思考は、重要なことに自分の時間とエネルギーを集中させる、という思考です。
もちろん、それがとても有意義に人生を生きる秘訣であることはわかります。
しかし、そのためには、いくつかのプロセスを踏む必要があります。
(1) 自分の価値観を知ること
これは、自分にとって何が重要なことなのかを明らかにすることです。
(2) 優先順位をつける
(3) 常に重要なことを選択する
ここでは、ウィルパワーが必要となります。
(4) 自分の使える時間を把握する
(5) 自分の時間を重要なことに配分する
(6) そのとおり「実行」する
ここも、ウィルパワーを消耗します。
こう書き出すと、結構大変なプロセスです。
これを自分のウィルパワーを使って行っていると、ウィルパワーを消耗してしまい、他のことに使えなくなってしまいます。
そこで、何とか自動化できないものか、と考えます。
その方法をYou Tubeで解説しました。
ご覧ください。
メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
所在不明株主がいる時
2021年05月27日事業承継や会社の売却等をしようとする場合に、少数株主で所在不明な株主がいる場合があります。
そうすると、事業承継をしても、将来紛争の不安が残りますし、M&Aの場合には、買い取ってくれない、という事態が想定されます。
そこで、早期に所在不明株主を解消しておく必要があります。
この馬合、まずは、所在不明株主が真の株主かどうかの調査から開始します。
名義株の問題です。
今回は、この方法は割愛します。
次に、所在調査を行います。
弁護士に所在不明株主の解消を依頼すると、住民票を追いかけて、調査をしてくれます。
事件処理を目的とした取得なので、住民票の取得のみを依頼しても受けてくれないでしょう。
どうしても判明しない場合は、どうしたらいいでしょうか。
会社法では、株主総会開催通知など、株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないとされています(会社法196条1項)。
そして、この場合において、当該株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかった場合には、会社はその株式を競売や買取りを行い、その代金を株主に交付することができます(会社法197条1項~3項)。
五年以上かかりますが、これにより、所在不明株主を解消することができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/ -
外注費が給与と認定された裁判例
2021年04月09日今回は、納税者が外注費として支払った金員が給与であると認定された裁判例をご紹介します。
令和3年2月26日判決(TAINS Z888-2352)です。
(事案)
●納税者は、塗装工事業等を営む株式会社であり、塗装工事に従事する従業員に対し、給与を支払っていたが、健康保険及び厚生年金保険に加入していなかった。●ある事業年度から、健康保険及び厚生年金保険に加入し、各人の給与から健康保険及び厚生年金保険に係る各保険料を徴収する旨説明したところ、従業員であった甲らから、給与が減額されるのは困るので、「外注先」として取り扱ってほしいとの申出があった。
●そこで、その後、甲らを外注先として扱い、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、甲らに対し、外注費として支払、甲らは事業所得として申告するようになった。
●税務調査が実施され、当該支払は、給与であると認定され更正処分、過少申告加算税賦課決定処分などがなされた。
(裁判所の判断)
●【事業所得】とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい
●【給与所得】とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、取り分け、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない(前掲最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決参照)。
●本件各作業員が予定されていた作業を休むこととなった場合には、原告が代替の作業員を手配していた。このことは、本件各作業員は、原告の他の従業員と同様、代替性が認められていなかったことを示すものである。
●本件各作業員は、本件支出金が支出されていた間も、従業員であった時期と同様に、原告から空間的、時間的な拘束を受け、原告の指揮命令に服し、原告に対して継続的ないし断続的に労務又は役務を提供していたものというべきであり、このことは、本件支出金の「給与等」該当性判断において最も重視されなければならない。
●本件各作業員には、完成すべき作業の定めはなく、依頼した作業が完成しなかったとしても、作業日数に応じた報酬が支払われていた。原告と本件各作業員との間で契約書は交わされておらず、危険負担についての定めもなかった。
●据置式の工具など高価な器具を所有しており、これを使用している場合には、事業者としての性格が強く、「給与等」該当性を弱める要素となる。本件についてみると、工具については、現場で着る作業着と手持ちの道具箱に入るくらいのコテとヘラを本件各作業員が用意し、それ以外の軍手、ハケ、ローラー、研磨機、マゼラーなどの道具や機械は原告から支給されたり貸与されたりしていた。これは、各作業員が従業員であった時期と同様であった。
===================
工事業者が、雇用契約から外注契約に変更しようとする相談は、よく受けるところだと思います。
たとえ、従業員本人の希望により外注契約にし、きちんと確定申告をしているとしても、実態が雇用契約であると判断されれば、給与と認定されてしまいます。
税理士が判断を誤った場合には、税理士損害賠償に発展する場合もあります。
また、税理士が給与と知りながら外注費として計上したことを理由として、懲戒処分を受けたケースもあります。
気をつけたいところです。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/ -
やることを絞り込もう
2020年12月01日今回のYouTube動画は、
「【他人の好意を獲得する方法】
心理学的アプローチ」です。
なぞかけもあります。
ぜひ、ご覧ください。
野球の大谷翔平選手は、投手として一流で、打者としても一流です。
投手と打者の「二刀流」と呼ばれています。
しかし、他に二刀流で成功した人は多くありません。
高校野球では、「四番ピッチャー」で投打に活躍する選手はある程度の数がいます。
しかし、プロになると、どちらかを諦めなければならなくなります。
なぜでしょうか。
2つの技術ともに一流を維持することが困難だからです。
力や時間を分散させなければならず、どちらも中途半端になってしまうからです。
学校に通っている時は、色々な科目の総合点で評価されるので、苦手科目を作らないように努力します。
私は大学時代、体育会の器械体操部に所属していましたが、体操競技では6種目も総合点で順位が決まるため、全ての種目を万遍なく練習する必要があります。
子供の頃は、何でもできる子がモテたりします。
社会に出るまでは、そのように、全てのことを万遍なくできるように努力をします。
その延長で、私たちは、「あれも、これも」と色々なことに手を出し、全てが中途半端に終わってしまっています。
しかし、社会に出ると、色々なことができる人よりも、一つのことに突出している人の方が成功を収めます。
色々なことができる人は、世の中に溢れかえっていますが、ある分野の人を求める際には、何でもできる人よりも、その分野に突出した能力を持っている人が選ばれます。
会社が独占禁止法の問題に直面した時、どの分野も扱っている弁護士に相談するより、独占禁止法を専門にしている弁護士に相談します。
成功するためには、できる限りやることを絞り込むことが大切だ、と言えるでしょう。
そして、そのためには、その他のことを全て諦めていく必要があります。
膨大な時間をある分野に注ぎ込むためには、他の分野を諦めて、そのことに時間を使わない、という覚悟が必要となります。
そして、それを実行するためには、根本的に考え方を変えていく必要があります。
それを21のエピソードとともに、じっくり解説しましたので、ぜひご一読を。
「超多忙な弁護士が教える時間を増やす思考法」(フォレスト出版)
https://www.amazon.co.jp/dp/486680100X/メルマガ登録は、こちら。
https://www.mag2.com/m/0000143169 -
成人した子が起こした交通事故で親の責任を認めた裁判例を弁護士が解説
2019年08月03日成人した子が起こした交通事故で親の責任を認めた裁判例を弁護士が解説します。
○判決
てんかん発作を起こしたクレーン車の運転者(事故当時26歳)による児童6人の死亡事故について、加害者と同居していた母親の責任も認めた判決(宇都宮地方裁判所 平成25年4月24日判決)
○事案の概要
平成23年4月18日午前7時43分ころ、栃木県鹿沼市内の道路を加害者がクレーン車で進行中、突然てんかんの発作が起きて意識を喪失し、通学のための歩道を歩行していた児童らにクレーン車を追突させ、児童6名が死亡した。
○判決要旨
以下の事情から、加害者の母親の不法行為責任を認めました。
・加害者の母親は、加害者と同居しており、加害者が小学校3年生のとき以来、てんかんに罹患していることを認識していたこと。
・加害者の母親は、加害者が高校を中退した平成13年8月以降は、加害者が抗てんかん薬を処方どおりに服用していなかったときには必ずてんかんの発作を起こしていたことを認識していたこと。
・加害者の母親は、加害者がてんかんに罹患しているため、自動車免許の欠格事由に該当することを認識していながら、加害者に原動機付自転車を買い与えたり、自動車教習所の費用を立て替えたり、普通自動車を買い与え、加害者が実際にてんかんの発作による交通事故を起こして自動車を破損させた後も、さらに新たな自動車を買い与えるなど、自動車の運転を継続することに積極的に加担してきたこと。
・クレーンの免許の取得についても、加害者がそれを取得することを単に黙認していたにとどまらず、運転免許試験当日の朝にてんかんの発作を起こしていた加害者を駅まで自動車で送り、免許の取得に加担したこと。
・加害者が本件事故の前に交通事故を5回も起こし、その原因がてんかんの発作であることを認識しながら、起こした事故の自動車運転過失致傷事件の裁判中に、事故原因について証言を拒むにとどめたのではなく、あえて加害者の供述内容に沿うように事故原因は事故前の寝不足である旨を証言したりするなど、嘘をついて加害者がてんかんであることを発覚するのを阻止したこと。
・事故当日の朝も、加害者の母親は、加害者が前日の夜服用すべきだった抗てんかん薬を服用していない状態で勤務先の会社へ出勤し、クレーン車等の運転を行うことを認識していたのであるから、会社に対して、加害者がてんかんに罹患していること、及び事故当日は抗てんかん薬を服用していないから特に発作を起こしやすい状態にあることを通報するなどしていれば、会社も加害者にクレーン車の運転をさせることはなく、事故を回避することができたと言えること。
○ポイント
民法では、未成年者が他人に損害を与えても、責任能力がない場合には損害賠償責任を負わないと規定されています(民法712条)。さらに、未成年者に責任能力がなく責任を負わない場合は、その監督すべき法定の義務のある者は、未成年者が第三者に与えた損害を賠償する義務を負うと規定されています(民法714条)。
ですので、未成年者が交通事故を起こして他人を死傷させた場合、その未成年者に責任能力が認められなければ、親が責任を負う場合があります。
なお、責任能力は、個別の事情や本人の能力等にもよりますが、おおむね12歳程度になれば認められるとされていますでは、成人して責任能力がある子が交通事故で他人を死傷させた場合に、親は責任を負うことがあるのか、という疑問に答えるのが、上記の裁判例です。
この裁判例では、親が、子がてんかんに罹患しており、子の運転行為により歩行者等の生命、身体及び財産に対する重大な事故が発生することを予見することができたこと、事故当日会社に通報することは容易であり、通報していれば事故の発生を防止することができたこと等の観点から、親の不法行為責任を認めたものです。
-
4歳の息子が交通事故の死亡事故に遭った場合、慰謝料は?
2019年08月03日交通事故で被害者が死亡した場合に、損害賠償額として請求できる項目には、主に以下のものが挙げられます。
①葬儀費
②死亡逸失利益
③慰謝料
④弁護士費用(裁判をした場合)
上記以外でも、即死ではなく、治療の後に死亡した場合は、実際にかかった治療費、付添看護費、通院交通費等を請求することができます。また、損害賠償を請求するために必要な診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書等の取得にかかった文書費等も、損害賠償関係費として請求できます。では、上述の4歳の男児が死亡した場合の損害賠償額がいくらになるのかを具体的にみていきましょう。弁護士が依頼を受けて交渉や裁判を行う場合、損害賠償額の算定については、日弁連交通事故相談センターが出している書籍「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」と言います)を使用しますが、この赤い本記載の基準を「裁判基準」といいます。以下の金額は裁判基準によりますが、通常、保険会社が示談の段階で提示してくる金額は裁判基準より低い場合がほとんどですので、注意が必要です。
①葬儀費
原則150万円で、150万円を下回る場合は実際にかかった額となります。
②死亡逸失利益
死亡逸失利益の算定式は下記の通りです。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、交通事故で死亡しなければ将来労働によって得られたであろう収入です。
幼児の場合、将来の収入額は不確定であるため、男性労働者の学歴計の全年齢平均賃金を基礎収入とします。生活費控除とは、基礎収入から、生きていればかかったはずの生活費分を差し引くことです。生活費控除率の目安は、被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合は40%、一家の支柱で被扶養者2人以上の場合は30%、女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合30%、男性(独身、幼児等含む)の場合は50%です。
したがって、4歳の男児の場合の生活費控除率は50%とします。就労可能年数は、原則として67歳までとなります。ただし、職種、地位、能力等によって、67歳を過ぎても就労することが可能であったと考えられる事情があるような場合には、67歳を超えた分についても認められることがあります。
ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合は将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引くことを「中間利息を控除する」という言い方をします。
4歳の男児の場合のライプニッツ係数についてですが、就労可能年数については、通常18歳から67歳までとするため、4歳の時点で損害賠償金を得るとすると、4歳から18歳までの期間について中間利息を控除する必要があります。そこで、4歳の男児の場合のライプニッツ係数は、4歳から67歳までの期間のライプニッツ係数から、4歳から18歳までの期間のライプニッツ係数を差し引いた数値を使用します。
したがって、
19.0751(4歳から67歳までの期間のライプニッツ係数)-9.8986(4歳から18歳までの期間のライプニッツ係数)=9.1765
が4歳男児の場合のライプニッツ係数になります。以上から、4歳男児の死亡逸失利益の計算式は以下のとおりです。
5,267,600円(賃金センサス平成23年男性学歴計全年齢平均賃金)×(1-0.5)×9.1765=24,169,066円
③慰謝料
被害者が一家の支柱の場合2800万円、母親・配偶者の場合2400万円、その他
(子供、成人独身者、高齢者等)の場合2000万円~2200万円が相場です。したがって、4歳の男児の場合として、2200万円を慰謝料とします。
④弁護士費用
弁護士に依頼し裁判により損害賠償を請求した場合、請求認容額の10%程度が弁護士費
用として認められます。この金額は実際に支払う弁護士費用とは無関係です。上述した請求額は、
1,500,000円(葬儀費)+24,169,066円(死亡逸失利益)+22,0
00,000円(慰謝料)=47,669,066円
となりますので、弁護士費用は47,669,066円の10%の4,766,906円
となります。したがって、4歳の男児が死亡した場合の損害賠償額の合計は、
1,500,000円(葬儀費)+24,169,066円(死亡逸失利益)+22,0
00,000円(慰謝料)+4,766,906円(弁護士費用)
=52,435,972円
となります。どうでしょうか?これが裁判のだいたいの基準です。
ただし、事情により増減します。
もし、自分に4歳の息子がいて、交通事故で死亡した場合、賠償金は、たった約5,000万円です。
低いですね。これでは、とても心の傷が癒えるはずがありません。
幼児の賠償額の増額を実現すべく、今後も頑張りたいと思います。
-
有名な名前を勝手に使うと犯罪に
2018年05月20日今回は、「有名な名前を勝手に使っちゃダメですよ」というお話です。
「勝手に“リクルート”名乗り逮捕 商号使用容疑、警視庁」(2018年5月18日 共同通信)
「リクルート」の商号を勝手に使い、「リクルートcom」と名乗る求人サイトをインターネットに立ち上げたとして、警視庁組織犯罪対策4課は、東京都江東区の無職の男(33)ら5人を不正競争防止法違反(著名表示冒用)の疑いで逮捕しました。
組対4課によると、容疑者の男らは全国の企業に電話で求人広告を無料で募り、一定期間の掲載後、今度は一転して「延長料金が払われていない」などと主張して料金を求めていたようで、2017年12月から今年4月までに、107法人から計約1280万円を集めたということです。
同課は、商号の無断利用を同法違反で摘発するのは珍しいとしています。
不正競争防止法は、1993(平成5)年に「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的として施行された法律です。(第1条)
同法で規定している「不法行為」にはさまざまあるのですが、よく知られているもののひとつが、いわゆる「企業秘密の漏洩」です。
製造技術のノウハウや販売マニュアル、顧客リストなど会社が持っている営業秘密を領得や開示、使用する罪ですね。詳しい解説はこちら⇒
「企業秘密の持ち出しは不正競争防止法違反」さて、今回ケースは「著名表示冒用」の疑いということですが、これはどのような罪なのでしょうか?
条文を見てみましょう。
「不正競争防止法」
第2条(定義)
1.この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
たとえば、シャネルやグッチ、ルイヴィトンなどの有名ブランドの名称を許可なく勝手に店名に使ってアパレル店などを営業すると不正競争防止法違反に問われる可能性があるということです。
過去には次のような事件があります。
・日本マクセル事件(大阪地裁平成16年1月29日判決)
カセットテープでなどの磁気テープや電池、光学部品等を製造販売する「マクセル」が、化粧品等を販売する株式会社日本マクセルを不正競争行為で訴えた事件。
日本マクセルは商号使用を認められなかった。・J-Phone事件(東京高裁平成13年10月25日判決)
通信事業者のジェイフォン東日本株式会社が、「j-phone.co.jp」のドメインを取得して使用していた水産物輸入販売会社「大行通商」に対して使用差止めなどを求めて訴えた事件。
「J-Phoneのホームページへようこそ!」などとホームページで表示していたことなどが問題となり、これらの行為が著名表示冒用と認められた。・アリナビック事件(大阪地裁平成11年9月16日判決)
「アリナミンA25」という商品名のビタミン製剤を販売していた原告が、「アリナビック25」という商品を製造販売していた被告を提訴した事件。
大阪地裁は、その類似性を認め著名表示冒用行為に当たると判断した。この法律では、他社がブランド名や商品名として使用しているものが「著名」かどうかについて争われます。
今回のケースでは、「リクルート」の名称が著名であること、また容疑者らが「広告料は無料」と言いながら、一定期間後に延長料を請求していた悪質性から逮捕になったと考えられます。
すでにある、誰もが知っているような著名な商品名やブランド名を使用して、信用や顧客吸引力などの価値に、ただ乗り(フリー・ライド)や希釈化(ダイリューション)、あるいは汚染(ポリューション)をすると、不正競争防止法違反に問われる可能性がある、ということは覚えておいてください。
なお、第2条では、不正競争のさまざまな類型を規定しています。
主なものは次の通りです。「周知表示混同惹起行為」(第1号)
既に知られているお店の看板に似せたものを使用して営業するなど。「著名表示冒用行為」(第2号)
ブランドとなっている商品名を使って同じ名前のお店を経営するなど。「商品形態摸倣行為」(第3号)
ヒット商品に似せた商品を製造販売するなど。「技術的制限手段に対する不正競争行為」(第11・12号)
CDやDVD、音楽・映像配信などデジタルコンテンツのコピープロテクトを解除したり、アクセス管理技術を無効にする機器やソフトウェア、プログラムなどを提供するなど。「原産地等誤認惹起行為」(第14号)
原産地を誤認させるような表示、紛らわしい表示をして商品にするなど。「競争者営業誹謗行為」(第15号)
ライバル会社の商品を特許侵害品だとウソを流布して、営業誹謗するなど。「代理人等商標無断使用行為」(第16号)
外国製品の輸入代理店が、そのメーカーの許諾を得ずに商標を使用するなど。※営業秘密に関しては第4~10号に規定。
みなさん、気をつけましょう。
-
子供への体罰と法律
2017年01月16日弁護士として、学校事故による子供のケガなどについての相談を受ける中で、親御さんから教師の体罰に関する悩みを聞くことがあります。
昨年末の報道によると、体罰は減少傾向にあるものの依然としてなくなってはおらず、高水準で推移しているようです。
「体罰で処分の公立教員721人 前年比減も高水準、文科省」(2016年12月22日 共同通信)
文部科学省の人事行政状況調査によると、2015年度に体罰を理由に懲戒や訓告などの処分を受けた公立学校の教員は721人で、前年度より231人減ったことがわかりました。
また、私立は166人(4人減)、国立は3人(1人減)で、国公私立校の合計は890人(236人減)だったということです。
体罰による教員の処分は、2011年度までは公立学校では300~400人程度で推移していました。
ところが、2013年1月に発覚した大阪市立桜宮高校の体罰問題を受け、2013年度は国公私立校で合わせて4000人超に急増。
2014年度は減少したものの、依然高い水準だとしています。なお、体罰以外も含む行為で処分された公立校の教員総数は6320人で、今回が初調査だった「いじめへの不適切な対処」については8人だったということです。
法的には、学校の教員には「懲戒権」が認められています。「学校教育法」
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
懲戒権というと何か強力な権利のようにも感じますが、ここでいう懲戒権とは、たとえば授業中にふざけている生徒を叱る、廊下に立っているように罰を与えるというような程度のものです。条文にもあるように、当然、体罰については認められていないことに注意が必要です。
しかし、人間は感情の生き物ですから、中には指導に力が入りすぎたり、ついカッと頭に血が上って生徒に体罰という暴力をふるってしまう教師がいることも事実です。
親御さんとしても、今後の学校との関係や子供の立場なども考えて、できるだけ事を荒げずに穏便に済ませたいと考える場合も多いでしょう。
ところが、体罰がエスカレートしていったり、子供がケガを負ったという事態にでもなれば、親として黙っているわけにはいきません。
そうした場合、親はどのように対処すればいいのでしょうか?
まず、刑事事件として警察に告訴することで、体罰をした教師は刑法上の罪に問われる可能性があります。
暴力を振るえば、「暴行罪」、暴力を振るった結果、怪我をすれば、「傷害罪」ということになります。
また教師は、非違行為があったとして学校から減給や停職、場合によっては免職などの懲戒処分を受けることになるでしょう。
さらに、民事での損害賠償請求をすることもできます。
この場合、国公立校であれば、親が請求する相手は教師個人や学校ではなく、都道府県や市町村という公共団体、場合によっては国になります。
「国家賠償法」
第1条
1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
一方、私立校の場合は、その教師の使用者である学校に対して損害賠償請求をすることになります。「民法」
第715条(使用者等の責任)
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
よって、教職員の故意または過失によって生じた事故では、その使用者として学校(保育所)が損害賠償義務を負うことになるのです。
親としては、学校との関係が今後も続いていくことを考えれば裁判にまで至る前に、まずは学校としっかり話し合いをするべきでしょう。それでも状況が改善されないようであれば、教育委員会に対して教師の懲戒処分を求めることも検討する必要がありますが、そのうえで訴訟も辞さないというのであれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
ご相談はこちらから⇒ http://www.bengoshi-sos.com/school/
-
TKC四谷支部総会で講演
2016年09月06日2016年8月5日に、TKC四谷支部総会で、講演しました。
タイトルは、「税理士賠償責任を回避するために(裁判事例・顧問契約書の文言等)」というものです。
税理士に専門家責任はとても重いものがあります。
税務顧問契約を締結する時は、ぜひ適切な契約書を締結していただければと思います。
関連記事
-
迷惑チラシのポスティングを禁止できるか?
2013年11月29日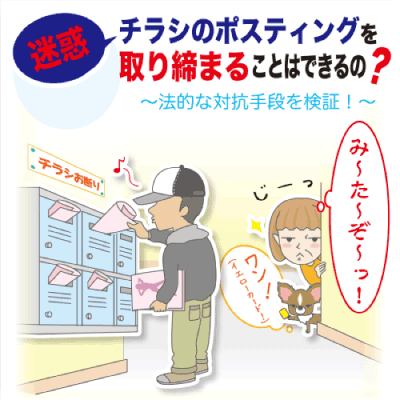
知らぬ間に、部屋中にいらないものがたまっている、気がつくと会社の机の上にも資料やコピーがたまって、いくつもの山脈ができている…。
そんな人、けっこう多いのではないでしょうか?
結局、自分でためてしまったものは、自分で片付けるしかありません。「整理術」に関する本も世の中にたくさんあります。
しかし、自分に関係のないところで、知らないうちにたまっていく厄介なものあります。
ポストに投函されているチラシも、そのひとつでしょう。
不動産、飲食店、通信販売、貸金、探偵、宅配サービス、不用品回収からピンクチラシまで、日々さまざまなチラシがポスティングされています。
整理しなければ、すぐにポストいっぱいにたまってしまって邪魔、他の郵便物も混ざっているから仕分けするのが面倒、そもそも頼んでもいないのに勝手に入れられて不愉快、など鬱陶しく感じている人も多いでしょう。
「チラシお断り」と張り紙しても、ほとんど効果はなし……では、こうしたチラシのポスティングを法的に拒否する、または取り締まる法律はあるのでしょうか?
軽犯罪法というものがあります。
これは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)、科料(1,000円以上1万円未満)に処する法律です。33の行為が罪として定められており、この中の32番目に、ポスティングに適用可能な規定があります。
軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
つまり、マンションの入り口などに「チラシ投函のための立入お断り」などの張り紙をしておけば、「入ることを禁じた場所」になり、入ってしまうと軽犯罪法1条32号により、軽犯罪法違反となります。
実際、居住者以外の立入を禁じたマンション等にちらし配布の目的で立ち入った場合にも同様の理由によって本号違反が成立するとされた例があるようです(東京簡裁略式命令平成4年8月18日公刊物未搭載のため未確認・出典「軽犯罪法101問」立花書房)。
また、さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は「住居侵入罪」に該当します。
刑法 第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。ちなみに、ピンクチラシなどは、各地方自治体の迷惑行為防止条例や青少年保護育成条例で規制されています。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、違反者は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます。
政治ビラについては、過去の判例で、住民からの再三にわたる投函禁止要請を無視し、思想を強要するビラを投函し続けた男に対し、この状況下においては住居侵入罪に当たるとの判決が下ったものがあります。
したがって、ポスティングをやめさせたければ、たとえば、マンションのポスト入り口などに「チラシ投函のための立入お断り。発見した場合は住居侵入罪及び軽犯罪法違反で刑事告訴します。監視カメラ作動中」などの掲示をし、監視カメラを設置する、という方法があります。
ところで、日本のチラシの歴史を調べてみると、1683(天和3)年、三井越後屋(今の三越)が呉服の宣伝で、「現金安売り掛け値なし」というキャッチコピーで出した「引き札」というチラシが最初のものだとされているそうです。
引き札は、独特な色合いと大胆な図柄が特徴で、今では収集家がいて展覧会も開かれる美術品だということです。
昔も今も、必要なチラシもあるので、すべてのポスティングが不用なものとはいえません。
そうなると、先ほどの禁止措置を講じた上で、マンションの管理組合が認めたチラシのみ、ラックなどを設置してチラシを入れておく、などの方法が考えられると思います(管理組合に広告収入も入ります)。
広告主よし、住人よし、管理組合よし、の三方よしですね。

















