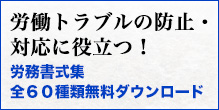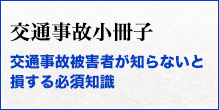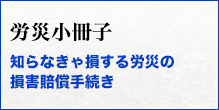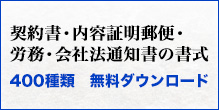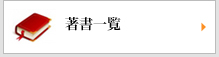-
法人が不法行為を受けた時の収益計上時期
2021年07月30日今回は、法人が詐欺など不法行為によって損失を受けた場合の課税関係について解説します。
法人が、詐欺など不法行為によって損失を受けた時は、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(法人税法22条3項3号)に該当し、損失が発生した年度の損金に計上すべき]
ものとされています(最高裁昭和43年10月17日判決)。そして、不法行為ということになると、損失と同時に、民法により、詐欺をした者に対する損害賠償請求権が発生しています。
これは、債権を取得した、ということになりますので、益金に計上することになります。
では、いつ計上すべきなのか、についてですが、法人税基本通達2-1-43があります。
===================
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
===================
この通達により
・原則として損金算入と同時に益金算入
・実際に支払を受けた事業年度に益金算入も認める
となります。
あとは、貸倒損失の要件該当性を検討することになります。
「回収可能性」の論点です。
そして、注意を要するのは、本通達の適用範囲は、「他の者」です。
「他の者」には、法人の役員または従業員は含まれない、と解されています(法人税基本通達逐条解説257頁)。
では、法人の役員または従業員の不法行為により損害を受けた場合には、どの事業年度に益金算入するのか。
これについては、裁判例もあり、長くなるので、後日、動画で解説したいとおもいます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/ -
最終報酬月額0円の場合、役員退職金をいくらにするか?
2021年06月18日今回は、「税理士を守る会」の会員の先生から寄せられた質問をご紹介します。
質疑内容は、一般化できるよう改変しています。
【質問】
これまで役員報酬がないまま事業を続けてきた法人の社長が退職するにあたり役員退職金を出そうとしています。
社長は他の他の収入を得ているので、特に役員報酬が必要なかったためです。
最終報酬月額が0円の場合は、どのように考えればよいでしょうか。
また、後日否認された場合の税賠も心配です。
【回答】
役員退職金については、裁判所は、原則として「功績倍率法」によっていることはご承知のことと思います。
功績倍率法が、最終報酬月額を基準にしているのは、
・役員の最終報酬月額は、特別な場合を除いて役員の在職期間中における最高水準を示す
・役員の在職期間中における会社に対する功績を最もよく反映している
ことを理由にしています(東京高裁平成元年1月23日判決他)。
しかし、会社によっては、上記が当てはまらない場合があり、その場合には、功績倍率法を採用することが適当でない、という場合もあります。
そのような場合には、「1年当たり平均額法」を採用する裁判例もあります(札幌地判昭和58年5月27日など)。
裁決例でも、「最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。」(昭和61年9月1日裁決抜粋)とされています。
ところが、この「1年当たり平均額法」も、同業類似法人の退職金を元に算出するので、納税者側では、正確に計算することができません。
そこで、裁判例の中には、・・・・
【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読んで解決することができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/ -
決算承認を経ない法人税申告は無効?
2021年02月19日今回は、「税理士を守る会」での質疑応答のご紹介です。
(内容を少し変えています)
(質問)
法人税法74条1項は、「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」とされており、「確定した決算」が必要とされています。
しかし、法人顧客からの税務申告依頼の際、株主総会議事録がないケースや、株主総会招集通知を発していないケースも多々あると思われます。
このような場合に、法人税の申告が無効となることはありますか?
何か念書のようなものをもらうには、どうしたらよいですか?
(回答)
定時株主総会による決算承認を受けた事実があるかどうかは、株主総会に出席しなければ確認ができません。
また株主総会議事録を作成していない中小企業も多いと推測されます。
それでも法人税の確定申告をしなければならないので、論点としては、
・定時株主総会による決算承認を得ない法人税確定申告の有効性
ということになります。
これが無効ということになると、日本中に無効な法人税申告が溢れかえることになるので、裁判所としても、有効にするロジックを構築してます。
過去の裁判例は、・・・
【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読むことができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/ -
遺留分侵害額請求権と小規模宅地の特例
2020年12月04日税理士向け記事です。
国税庁より、遺留分侵害額請求にかかる質疑応答事例が公開されましたので、ご紹介します。
すでに知っている先生は、読み飛ばしていただければと思います。
【タイトル】遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)
【照会要旨】
被相続人甲(令和元年8月1日相続開始)の相続人は、長男乙と長女丙の2名です。乙は甲の遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)及びB宅地(特定事業用宅地等)を遺贈により取得し、相続税の申告に当たってこれらの宅地について小規模宅地等の特例を適用して期限内に申告しました(小規模宅地等の特例の適用要件はすべて満たしています。)。その後、丙から遺留分侵害額の請求がなされ、家庭裁判所の調停の結果、乙は丙に対し遺留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなりましたが、乙はこれに代えてB宅地の所有権を丙に移転させました(移転は相続税の申告期限後に行われました。)。
丙は修正申告の際にB宅地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。【国税庁による回答は、ウェブサイトで】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/01/05.htm
====================
上記について、法的な解説をします。
答えとしては、
・乙には譲渡所得税
・丙は小規模宅地の特例は不適用
となります。
原理は、同じです。
2020年7月1日より前に開始された相続では、不動産について、遺留分減殺請求権が行使された時、不動産は物権共有となっていました。
しかし、相続法改正により、遺留分侵害額請求は、【金銭請求】となりました。
したがって、たとえば、不動産について、遺留分侵害額請求権を行使した場合には、物権共有ではなく、「金●●円の請求権」となります。
そうすると、乙から見ると、「金●●円の債務」となるわけで、この債務を不動産の所有権を丙に移転することにより、債務を消滅させる、ということになるので、法律上、「代物弁済」となります。
ということは、乙は、その所有する不動産を丙に譲渡して債務を消滅させた、ということになるので、通常の不動産譲渡と同様に、譲渡所得税の課税問題となります。
そして、丙は、金銭請求権の弁済に代えて不動産の所有権に移転を受けた、ということになるため、「相続又は遺贈により取得した」ことにはなりません。
したがって、小規模宅地の特例の要件を満たさない、という結論になります。
法律上の性質を知っていれば類似事例も全て解決できると思いますが、結論だけ憶えていると、基本的なことでも「あれ?」となることもあるかと思いますので、念のための解説でした。
-
質問応答記録書に署名押印しないと?
2020年11月18日さて、今回は、「質問応答記録書」についてです。
税務調査の過程で、質問応答記録書が作成さ
れることがあります。
質問応答記録書は、租税職員が質問し、納税
義務者等が回答した際に、その内容を記録し、
記録後に回答者に対して署名押印を求めるものです。
従前は、租税職員が質問し、納税義務者等が
回答した内容を証拠に残す際には、納税義務
者等の回答内容を書面に記載して、申述書、
確認書、供述書、嘆願書などの表題の書面を
作成して、納税義務者等の署名押印を得るこ
とが多かったと思います。
この扱いが、平成25年6月から、質問応答
録取書の作成に改められたものです。
関連文書としては、
●平成25年6月の国税庁課税総括課作成の
「質問応答記録書作成の手引」
●平成29年6月30日課税総括課情報
「質問応答記録書作成の手引について(情報)」
があります。
質問応答記録書は、
「事案によっては、この質問応答記録書は、
課税処分のみならず、これに関わる不服申立
て等においても証拠資料として用いられる場
合があることも踏まえ、第三者(審判官や裁
判官)が読んでも分かるように、必要・十分
な事項を完結明瞭に記載する必要がある」
(手引)とされており、更正するかどうかを
判断する上での証拠資料となるのはもとより、
処分取消訴訟等において証拠として提出され
ることが前提とされています。
そして、質問応答記録書は、回答者には交付
されません。
また、「証拠書類等の客観的な証拠により課税要件
の充足性を確認できる事案については、原則
として、質問応答記録書等の作成は要しない
ことに留意する」(手引)
とされていることから、質問応答記録書が作
成が開始される事案は、原則として、それま
での調査により収集された客観的な証拠では
、課税要件の充足性を確認することができな
いと判断されていることがわかります。
質問応答記録書は、納税者が署名押印を拒否しても、
調査担当者が回答者が署名・押印を拒否したことや
その理由などを奥書し、署名押印することで書類としては完成します。
そして、一度完成すると、その後、訂正・追加・
削除等を申し立てても、訂正等を行ってはならないと
されていますので、誤りがある場合には、その場で申立て、
記載してもらう必要があります。
-
給与所得と事業所得の区別の例示
2020年09月22日今回は、給与所得と事業所得の区別基準です。
情報公開により取得された国税局の内部文書を整理しました。
東京国税局 平成15年7月 第28号法人課税課速報(源泉所得税関係)(TAINS H150700-28)です。
この中に、実務において、給与所得と事業所得を判定する際に参考となる例示が記載されています。
ある事実関係があると、給与所得と事業所得のどちらに判例が傾くか、という例示です。
===================●給与所得の認定に傾く例示
労働基準法の適用を受ける
支払者が作成している組織図・配席図に記載がある
役職(部長、課長等)がある
服務規程に従うこととされている
有給休暇制度がある
他の従集員と同様の福利厚生を受けることができる(社宅の貸与、結婚祝金、レクリェーション、健康診断等) |
通勤手当の支給を受けている他の従業員と同様の手当を受けることが可能(住居手当、家族手当等)
時間外(残業)手当、賞与の制度がある退職金の支給の対象とされている
労働組合に加入できる者である
支払者からユニフォーム、制服等が支給(貸与)されている
名刺、名札、名簿等において支払者に帰属しているようになっている
業務に当たって、支払者側のマニュアルに従うこととされている
支払者の作ったスケジュールに従うこととされている
本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令により、他の業務を行うことがある
勤務時間の指定がある
勤務場所の指定がある
旅費、交通費を会社が負担している
報酬の最低保障がある
その対価が材料代等の実費とそれ以外に区分して請求される
●事業所得の認定に傾く例示
支払を受ける者の提供する労務が許認可を要する業務の場合、本人は資格を有している(例 運送業)
その業務に係る材料等の在庫を自己で保管している報酬について値引き、値上げ等の判断を行うことができる
その対価の支払者以外の顧客を有しているか
以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていた店舗を有し一般客の求めに応じているものである
その対価の支払者以外の者からの受注を受けることが禁止されている
同業者団体の加入者である
使用人を有している者である
支払を受ける者がその業務について自己の負担で損害保険等に加入している
業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が行う
遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が支払われないほか罰金(報酬の減額)がある
その対価に係る請求書等の作成がされている
その対価が経費分も含めて一括で請求されている==================
関与先で行われている金員の支払の判定の際に参考にしていただければと思います。
また、たとえば、事業所得と判定したのであれば、実際の運用を、上記の【事業所得の認定に傾く例示】が多く含まれるように関与先に助言指導をしていくことをおすすめします。
微妙な判定になる場合には、説明と将来否認される可能性がある旨の証拠化もおすすめしたいと思います。
-
事業所得と雑所得の判断基準の要素
2020年09月10日今回は、事業所得と雑所得の判定をする際に、どのような要素を検討すべきか、についてご紹介します。
雑所得と認定されると、以下のようなものが否定されることになります。
・給与所得等他の所得との損益通算
・純損失の3年の繰越し・繰り戻し
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の適用
・事業所得に認められる各種優遇税制の適用
(最高裁昭和56年4月24日判決・弁護士顧問料事件)では、事業所得は、次のような業務から生ずる所得とされています。
(1)自己の計算と危険
(2)独立して営まれ
(3)営利性、有償性を有し
(4)反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務
これを更に詳しくしたのが、名古屋地裁昭和60年4月26日判決で、次のような判断基準を挙げています。
==================
・経済的行為の営利性
・有償性の有無
・継続性、反覆性の有無
・自己の危険と計算による企画遂行性の有無
・当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度
・人的、物的設備の有無
・当該経済的行為をなす資金の調達方法
・その者の職業、経歴及び社会的地位
・生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か
⇒等の諸要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべきである
==================
では、これらの基準に照らし、実際の事例でどう判断されたかについてですが、これは、別の機会にYouTubeで解説していきたいと思います。
-
給与所得の事業所得の区別の判断基準(最高裁判決)
2020年08月31日今回は、所得税法上の給与所得と事業所得の区別の判断基準について、有名な最高裁判決を確認しておきたいと思います。
ある役務の提供が給与所得か事業所得かを判断するについては、消費税基本通達1-1-1を参考にしている先生も多いと思います。
しかし、同通達は、「出来高払いの給与と請負による報酬」の区分に関する判断基準を示しているもので、総括的に給与所得と事業所得の区分に関する判断基準を示しているものではありません。
同通達は、次のような表現となっています。
===================
出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
===================
そして、請負契約を前提とした4要素が示されているわけです。
したがって、これに当てはまらない場合には、給与所得と事業所得の区別の判断基準を示した最高裁判決の基準に照らして検討することになるかと思います。
(最高裁昭和56年4月24日判決・弁護士顧問料事件)です。
弁護士の顧問料が給与所得か事業所得かが争われた事案です。
何度もお読みになった先生が多いかと思います。
同判決では、事業所得は次の要素を持っているとされています。
(1)自己の計算と危険
(2)独立して営まれ
(3)営利性、有償性を有し
(4)反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務これに対し、給与所得は次の要素を持っているとされています。
(1)指揮命令に服して労務提供
(2)空間的、時間的な拘束
(3)継続的ないし断続的に労務又は役務の提供そして、同判決では、弁護士の顧問料を事業所得としています。
理由は、以下のとおりです。
===================
(1)各顧問契約には勤務時間、勤務場所についての定めがない(時間的、空間的拘束の否定)
(2)契約はその頃常時数社との間で締結されており、特定の会社の業務に定時専従する等格別の拘束を受けるものではない(指揮命令、時間的拘束の否定)
(3)契約の実施状況は、多くの場合電話により、時には右各社の担当者が法律事務所を訪れて随時法律問題等につき相談するため、弁護士が出向くことはない(指揮命令、空間的拘束の否定)
(4)相談回数は会社によつて異なり、月に二、三回というところや半年に一回、一年に一回というところもある(継続的、断続的労務提供、時間的拘束の否定)
(5)各社はいずれも本件顧問料を弁護士の業務に関する報酬にあたるものとして支払っており、各種保険料などを控除しておらず賞与等も払っていないので、雇用契約と認識していない。(当事者の認識)
===================
消費税基本通達1-1-1も、この基準を請負契約に当てはめたものと考えられます。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。(時間的・空間的拘束の有無、独立性の有無))
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。(指揮命令)
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。(自己の計算と危険の有無、継続的役務提供の対価)
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。(自己の計算と危険の有無、独立性の有無)
したがって、通達で当てはまらない場合には、最高裁判決に立ち戻って判断するのがよいと思います。
-
コロナ禍で役員報酬減額⇒増額は許される?
2020年06月30日今回は、コロナの影響で期中で役員報酬を減額したものの、業績が回復したために同期中に増額することは許されるか、という論点を検討したいと思います。
まずは、減額です。
この点については、4月13日付で、国税庁から情報が追加されております。
新型コロナウイルスの影響で期中に役員報酬を減額した場合に業績悪化改定事由に該当する場合が記載されております。
解釈としては、従前と変わるところはなく、客観的な状況が要求されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
法令、通達上の要件としては、以下のとおりです。
===================法人税法施行令69条1項1号ハ
ⅲ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これ
に類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与
の額を減額した改定に限り、ⅰ及びⅱに掲げる改定を除きます。)===================
法人税基本通達
9-2-13 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
===================
ここの記載にあるように、
・一時的な資金繰りの都合
・単に業績目標値に達しない
場合は、業績悪化に該当しない、ということに注意が必要です。
客観的に業績が悪化していないのに、「コロナの不安から」というだけで、実際にも業績が悪化していないのであれば、「客観的事情」がなく、利益操作との認定がされる恐れがあると思います。
そして、この問題が問われるのは、後日の税務調査時になりますので、「業績が悪化したことを示す客観的資料」を残しておくことが重要ということになります。
次に、増額。
この後、業績が回復した場合に、役員給与を元の金額に増額するのは、どうか、という点ですが、もう一度法令上の要件を確認します。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
から抜粋。
===================
(1) その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(法法 34(1)一)
(2) 定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの(法令 69(1)一)
ⅰ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定(法令 69(1)一イ)
ⅱ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務
の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により
されたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(ⅰに掲げる改定を除きます。)(法令
69(1)一ロ)ⅲ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これ
に類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与
の額を減額した改定に限り、ⅰ及びⅱに掲げる改定を除きます。)(法令 69(1)一ハ)
(3) 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法令 69(1)二)===================
以下は、私見です。
期中に減額した後、同期中にまた増額して元に戻すことが許されるのは、上記(2)のⅱの属人的事情の場合と解されます。
つまり、職務内容の重大な変更などの
●属人的事情により減額⇒属人的事情により増額
は、認められる余地があります。
たとえば、業務担当役員が、
(1)コロナによる休業により職務がなくな
って減額
(2)宣言解除により職務が復活して増額
というような場合です。
しかし、業績悪化は、上記(2)のⅲでは、「減額した改定に限り」とされていますので、増額した改定については、除外されております。
したがって、
●業績悪化により減額
認められますが、
●業績悪化により減額⇒業績回復により増額
は、今後、法令・通達等が改正されない限り、認められないと考えます。
利益操作の余地を残してしまうためです。
この場合、減額された役員報酬額が定期同額給与額になり、それを超える部分が損金不算入になります。
一旦減額してしまったものの、どうしても増額したい場合は、決算期を前倒しする、という方法もありますので、ご検討ください。
-
「遺言によらない遺産分割」の法的理解と税務的理解
2020年05月30日今回は、「遺言によらない遺産分割」の法的理解と税務上の実務運用の相違点について解説をします。
まずは、法的理解からです。
遺言は、被相続人の死亡により、ただちにその効力を生じます。
たとえば、「土地建物を長男Aに相続させる」と記載があれば、被相続人の死亡によってただちに相続の効力が生ずる、ということです。
遺贈であれば個別に放棄できますが、上記の遺言の場合、遺言の効力を生じさせないためには、相続放棄をし、はじめから相続人でなかったことにします。
しかし、実務では、法定相続人全員で協議し、相続放棄をすることなく、「遺言によらない遺産分割」をすることがあります。
これを法的に理解するとどうなるか、というと、
・遺言は被相続人の死亡によりただちに効力を生ずる
・効力を生じさせないためには、相続放棄
ということになりますから、「遺言によらない遺産分割」の場合には、相続放棄をしないわけですから、すでに遺言の効力が生じていることになります。
上記の例で言えば、被相続人の死亡により、遺言の効力が生じ、土地建物が長男に相続された、ということです。
そして、その後、法定相続人間の協議により、贈与や交換、売買等がなされた、という理解になります。
しかし、この理解を税務の実務に適用してしまうと、
・遺言どおりに相続税を課税
・遺産分割により贈与税、所得税などを課税
となり、納税者の負担が大きいことになります。
また、実態として、担税力は1度しか生じていないのに、2度課税をする、ということにもなりかねません。
そこで、税務上は、この場合に1度の課税になるように解釈運用されています。
国税庁Q&Aでは、次のようにされています。
文言としては「遺贈」ですが、「相続させる」旨の特定財産承継遺言でも、実務では同様の扱いだと思います。
=================
No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。
===================
この「遺言によらない遺産分割」と異なるものに、「遺産分割のやり直し」があります。
いったん遺産分割が成立した後に、その遺産分割協議を合意解除して、再分割をする、という方法です。
これも法律上は可能ですが、このケースでは、当初の遺産分割に錯誤が認められない限り、当初の遺産分割で相続税が課税され、2回目の遺産分割で贈与税や所得税が課税されるというのが理論的帰結となりますので、注意したいところです。