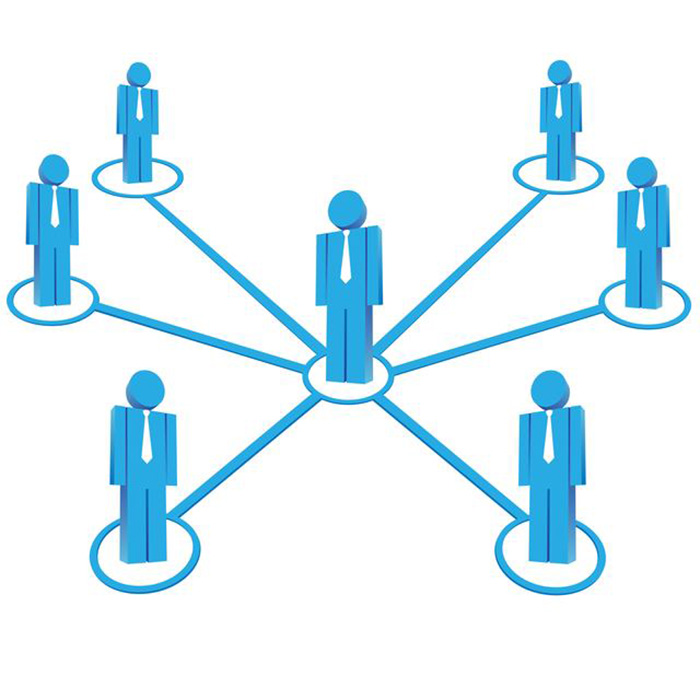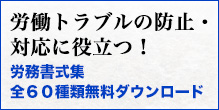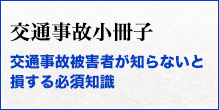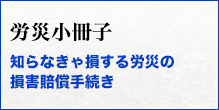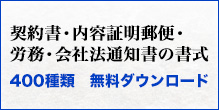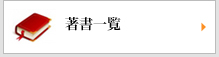立証責任で課税庁が敗訴した裁判例
課税要件事実に関する立証責任については、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決、月報9巻5号668頁)とされており、課税庁に立証責任があるのが原則です。
したがって、課税庁は税務調査によって事実を調査し、証拠を収集し、課税処分をする場合には、後日処分取消訴訟などで争われたとしても、立証に成功すると判断することが必要となります。この判断を誤り、後日の処分取消訴訟等で立証に失敗した場合には、課税処分が違法となります。
では、「立証した」とは、どういうことなのか、あるいは、「立証していない」というのはどういうことなのでしょうか。
実際の裁判例で見てみましょう。
東京高裁平成15年1月29日判決のアルゼ事件があります。
事案としては、納税者Xが、A社からパチスロ機のメイン基板合計6万6455枚を1枚当たり1万4000円で購入し、これらをB社に対し1枚当たり8万円で販売する取引をして43億8603万円の売買利益を得ていたにもかかわらず、米国法人C社がこの取引をしていたかのように仮装し、同取引によって得た所得等を申告しなかったとして、消費税及び地方消費税について、それぞれ更正処分及び重加算税賦課決定処分をした事案です。
課税庁は、本件各取引が、売買契約の内心的効果意思のない通謀虚偽の意思表示によるもので無効であるにもかかわらず、取引があるように仮装したものである、と主張しました。
課税町に立証責任がある、ということは、この「通謀虚偽表示」と、「取引の仮想」を立証する責任がある、ということです。
裁判所は、各種証拠を検討した上で、本件各取引が、「いずれも通謀虚偽の意思表示によるものであって、被控訴人が明立から明立基板を購入しこれをECJに販売したものであると認めることはできず、他に、これを認めることができる的確な証拠はない。」として、納税者勝訴判決をしました。
本裁判例では、裁判所が、重加算税の課税要件事実の主張立証責任が国にあることを前提とした上で、重加算税の課税要件事実の立証が成功しなかったとして、立証責任により国敗訴判決をしたものと理解しています。
また、主張立証責任が問題となった事例に、東京高裁平成27年3月25日判決(判例時報2267号24頁)のIBM事件があります。有名な事件です。
上告審は上告不受理決定です。
この事案は、日本IBMの全株式を保有していた納税者Xが、自己の保有する日本IBMの株式を日本IBMに譲渡した上で、Xと日本IBMが連結納税者制度の適用を選択しました。株式譲渡によりXには約4000億円の損失が発生していたことから、当時の法制度によると、日本IBMが国内で事業活動を行うことによる所得何年にもわたり繰越欠損金と相殺されて、課税されない状態が続くことになりました。
そこで、課税庁は、法人税法132条の同族会社の行為計算否認規定を適用して、課税処分を行ったというものです。
法人税法132条は、「税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。」と規定しています。
本件では、一連の行為が、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となる」に該当するかどうかが争われたものです。
裁判所は、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となる」かどうかの判断基準として、「法人税法132条1項の趣旨に照らせば、同族会社の行為又は計算が、同項にいう『これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』か否かは、専ら経済的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不合理、不自然なものと認められるか否かという客観的、合理的基準に従って判断すべきものと解される〔最高裁昭和53年4月21日第二小法廷判決・訟務月報24巻8号1694頁(最高裁昭和53年判決)、最高裁昭和59年10月25日第一小法廷判決・集民143号75頁参照〕」と規範を定立しました。
その上で、本件一連の行為が、独立当事者間の通常の取引と異なるものであり、経済的合理性を欠くとの国の主張について、「本件各譲渡が、本件税額圧縮・・・の実現のため、被控訴人の中間持株会社化・・・・と一体的に行われたという控訴人の主張は、本件全証拠によっても認めることができないというほかない」と判示し、また、本件一連の行為が、全体として独立当事者間の通常の取引と異なるものであり、経済的合理性を欠くとの国の主張について、「そもそも、控訴人は、本件各譲渡が独立当事者間の通常の取引と異なると主張しているのにもかかわらず、独立当事者間の通常の取引であれば、どのような譲渡価額で各譲渡がされたはずであるのかについて、何ら具体的な主張立証をしていない」として、主張立証責任を理由に納税者勝訴の判決をしました。
したがって、税務調査において、調査担当者から税務処理を否認された場合でも、課税庁の主張する課税要件に該当するかどうかの立証責任は課税庁にあることを明確にし、その上で、課税要件事実が立証しきれているかどうかを吟味する必要があります。
とは、言っても、「立証しきれているかどうか」は、どうやって判断するか、わからない、という疑問があるかもしれません。
これは、「証明度」の問題です。
事実をどの程度、証拠によって「証明」すれば、裁判所に事実を認定してもらえるのか、とうい問題です。
証明度に関しては、有名な判決があります。「ルンバール事件判決」です。
ルンバ-ル事件判決(最高裁昭和50年10月24日判決、民集29巻9号1417頁)は、化膿性髄膜炎に罹患した幼児の治療として、医師が「ルンバール」という治療をした後に幼児にけいれん発作等及び知能障害等の病変が生じたことについて、同病変等がルンバール施術のショックによる脳出血によるものと認定できるかどうかが争われた事案です。
この事案において、最高裁は、証明度について、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」と判示しています。
そして、経験則を用いて、病変等がルンバール施術のショックによる脳出血によるものと認定しました。
この裁判例から、証明度について次のことが言えることになります。
①立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない
②経験則に照らして全証拠を総合検討する
③因果関係については高度の蓋然性を証明する
④通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる
したがって、税務調査において、課税庁から納税者の税務処理を否認された場合には、課税等が主張する課税要件事実が、収集された証拠により、この証明度に達しているかを吟味する必要があります。
ご相談は、こちらから。
https://www.bengoshi-sos.com/zeimu/
「税務のわかる弁護士が教える税務調査に役立つ”整理表” -納税者勝訴判決から導く”七段論法” 」(ぎょうせい)
https://www.amazon.co.jp/dp/4324106460/