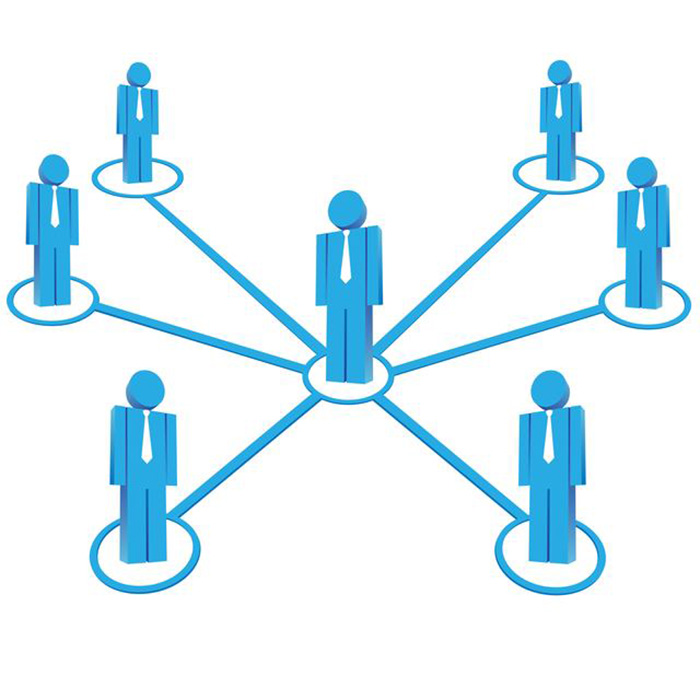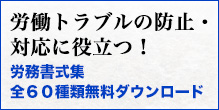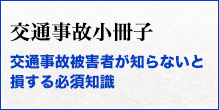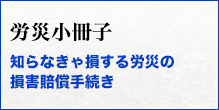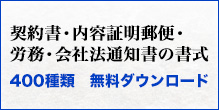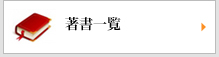税務調査でも法的三段論法に当てはめる
法的三段論法とは
裁判所が判決を出す時には、法的三段論法にあてはめて結論を出します。また、課税庁が更正をするときにも、法的三段論法を適用することとなります。
三段論法とは、たとえば、「動物は死ぬ」、「ゾウは動物である」、「ゆえに、ゾウは死ぬ」というように大前提、小前提、結論という三段階の推論のことです。
これを法律の適用過程に応用したのが法的三段論法で、法規範を大前提とし、事実を小前提として、法規範に事実を当てはめて判決という結論を出すことになります。
税務調査においても、法的三段論法の考え方に従って行われます。
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)第2章1の1」では、「調査とは、国税・・・に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいうことに留意する。」とされています。
したがって、税務調査において、調査官から否認指摘があった際には、その指摘が法的三段論法に照らして正しいかどうかを検討することになります。
たとえば、納税者が離婚の際に不動産を財産分与した場合について、財産分与による所有権の移転は、譲渡所得が発生しないとして所得税の確定申告をした時に、税務調査の結果、不動産の財産分与も所得税法上の「資産の譲渡」に該当するとして、更正を行うこととします。
この場合には、法的三段論法にあてはめ、(1)所得税法にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいう(最高裁昭和50年5月27日判決、百選第6版42)、(2)財産分与は、資産を配偶者に移転するものである、(3)ゆえに、財産分与も「資産の譲渡」に該当する、という結論を出し、資産の増加益に関して更正を行うこととなります。
更正を行う際の法規範、事実、法規範への事実の当てはめ、の三段階のいずれかに誤りがあれば、更正にも誤りがあることになります。したがって、税務調査の際には、法的三段論法の三段階において誤りがないかどうか、検討する必要があります。
法規範とは
法規範というのは、租税法規の条文を意味するのはもちろんですが、条文だけでは、その意味内容を確定することはできません。
たとえば、所得税法33条の「資産の譲渡」といっても、どの範囲のものが「資産」に含まれるのか、「譲渡」は有償に限るのか、無償の譲渡も含まれるのか、については条文からは明らかでないので、それらを解明することが必要です。それが、法解釈となります。法解釈とは、「実定法の規範的意味内容を解明する作業」をいうとされています。
法解釈には、文理解釈・論理解釈・歴史的解釈・目的論的解釈、など複数の技法があります。
ここでは、文理解釈のみ説明します。
文理解釈とは、法規の文字・文章の意味をその言葉の使用法や文法の規則に従って確定することによってなされる解釈です。
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とし、84条で、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」として、租税法律主義を定めています。
そして、租税法律主義は、課税要件法定主義、課税要件明確主義を要請します。課税要件は、納税義務ないし租税債務が成立するための要件です。課税要件法定主義および課税要件明確主義からは、納税義務を成立されるための要件は、法律又はその具体的・個別的委任による政省令等で定められることが必要であり、かつ、その定めは可能な限り一義的で明確である必要があります。さらに、その明確に定められた要件は、その文理に従って解釈されなければなりません。
したがって、租税法規の解釈は、文理解釈が原則となります。
ホステス報酬に係る源泉徴収について争われた事案において、最高裁平成22年3月2日(百選第6版13事件)は、「租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく、原審のような解釈を採ることは、・・・文言上困難」と判示し、所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」について、「当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然」であると判示しています。
事実(小前提)
更正を行う際には、法解釈の各技法によって租税法規の規定の意味内容を解明し、それに事実を当てはめる作業を行います。
したがって、更正にあたっては、必ず事実を認定する作業が行われることになります。
しかし、場合によっては、事実があるかどうか認定できない、という場合もあります。このような場合に、いずれか一方の当事者が負う不利益又は負担のことを「立証責任」といいます。
そして、事実認定においては、立証責任を負担する当事者が、「どの程度まで立証」すれば、証明できたことになるのか、という「証明度」も考える必要があります。立証責任を負担する者の立証が、証明度に達しないときは、その主張する事実が認定できず、不利益又は負担を負うことになります。
課税庁が更正をする際には、後日、処分取消訴訟において勝訴できることを前提としています。そして、課税庁が立証責任を負担する事実について、証明度に達する立証ができない時は、更正処分が取り消されることになりますので、事実認定は重要な作業ということになります。
米国関係会社を経由した迂回取引かどうかが争われたアルゼ事件において、東京高裁平成15年1月29日判決は、提出された証拠によっては、国の主張する事実を「認めることはできず、他に、これを認めることができる的確な証拠はない」として、立証責任により、国側敗訴判決を出しました。
したがって、税務調査において、課税庁が納税者の税務処理を否認する旨の主張をしている際には、課税庁が収集した証拠によって、課税庁の主張する税務処理の課税要件事実の立証が証明度に達しているかどうかを吟味することが必要となってきます。
法適用(当てはめ)
法を適切に解釈し、事実を適切に認定しても、法規範に事実を認定するあてはめが違法となる場合があります。
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるかどうかが争われた事案において、法解釈が正しく、事実も国の主張どおりであるとしても、通達を変更した際には、通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要な措置を講ずべきものである」として、それを怠っていたことを理由として、国側の主張を認めなかった最高裁平成18年10月24日判決(判例時報1955号37頁)があります。
税務調査における攻防は口頭でやり取りされることが多いと思いますが、課税要件該当性を判断するには、必ず三段論法に当てはめることが必要となります。
ご相談は、こちらから。
https://www.bengoshi-sos.com/zeimu/
「税務のわかる弁護士が教える税務調査に役立つ”整理表” -納税者勝訴判決から導く”七段論法” 」(ぎょうせい)
https://www.amazon.co.jp/dp/4324106460/