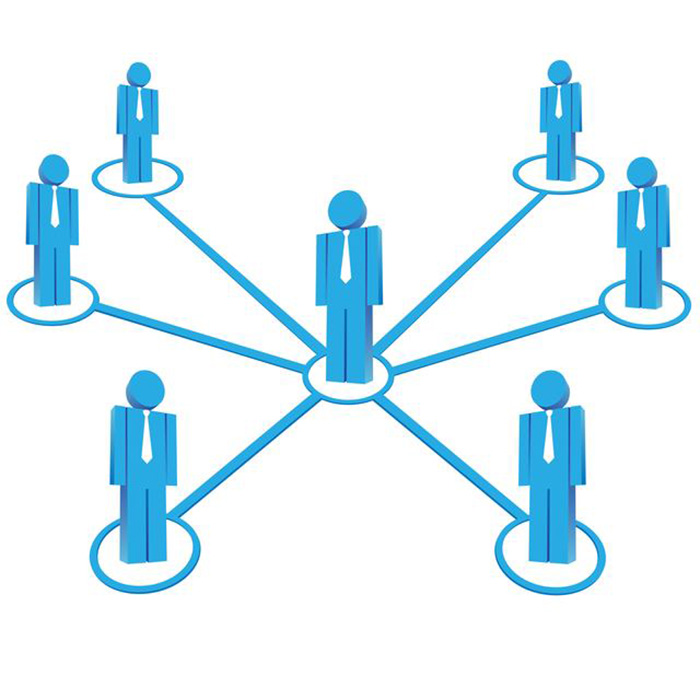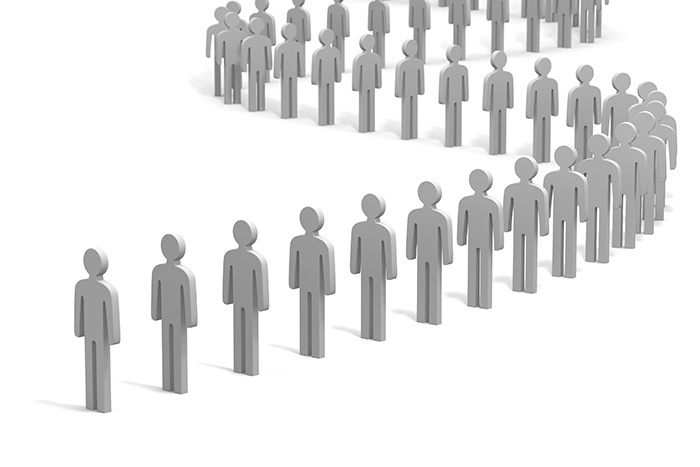やらない後悔の大きさ
あなたは今、心の中で「やってみたいけれど、足踏みしていること」はありませんか?
転職、新しい趣味、あるいは大切な人への告白や謝罪かもしれません。
一歩踏み出すには勇気が必要です。
「失敗したらどうしよう」「今のままでも十分幸せなのではないか」と、現状維持を選ぶ理由を探してしまうのが人間です。
しかし、人生の最期に振り返ったとき、私たちはどのような決断を悔やむことになるのでしょうか。
心理学者、トーマス・ギロビッチ氏とビクトリア・メドヴェック氏は、1995年にある研究結果を発表しました。
彼らの調査によると、人々は「短期的」には行動して失敗したことを後悔する傾向がある一方で、「長期的」に見ると、行動しなかったことを圧倒的に強く後悔するということです。
つまり、直後は「あんなこと言わなければよかった」「失敗して恥をかいた」と行動したことを悔やみますが、時間が経つにつれてその痛みは薄れ、代わりに「なぜあの時、挑戦しなかったのか」という後悔が亡霊のように現れ、長く心に留まり続けるのです。
これには「ツァイガルニク効果」が関係していると考えられます。
これは「達成できた課題よりも、達成できなかった(あるいは中断した)課題の方をよく覚えている」という記憶の特性です。
「やってしまった失敗」は、結果が出て完結しているため、人は心理的な整理(正当化や反省)をつけて乗り越えることができます。
しかし、「やらなかったこと」には結末がなく、「もしあの時、勇気を出していたら、素晴らしい未来があったかもしれない」という無限の「IF(もし)」の物語が頭の中で膨らみ続け、いつまでも完結しないことになります。
そう考えると、何にでも挑戦した方がいいことになりますが、事はそう簡単ではありません。
・一歩を踏み出すのは難しい。
・続けるのは難しい。
・失敗した自分を許すのは難しい。
など、いくつものハードルを超えなければならないためです。
このようなハードルの一つ一つを乗り越えるための、自分なりの自己コントロール法を身につけておくことが大切です。
ぜひメルマガに登録を。
https://www.mag2.com/m/0000143169