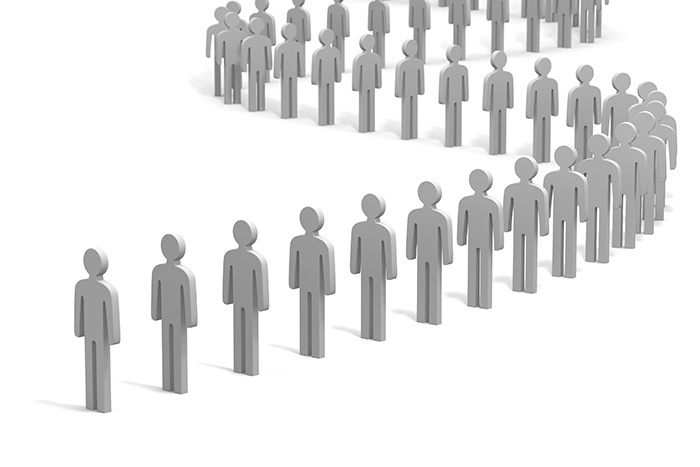なぜ教えると記憶に定着するのか?
私は、年に何度も税理士会等で税理士向けの研修講師を依頼されます。
そうすると、自分が受講者になって学ぶより研修内容を深く理解することができます。
「他人に教えると、自分の理解が深まる」とは、昔から言われていることですね。
その話をする前に、あなたは、今、何かを学ぶ意欲を持って、実際に学んでいますか?
もし、そうでないなら、老化が進行する可能性があります。
脳の可塑性により、新しいことを学んだり、新しい経験をしたりすると、脳の神経細胞(ニューロン)同士のつながり(シナプス)が強化され、新しい神経回路が形成されます。
しかし、学びをやめてしまうと、新しい神経回路が形成されず、衰える方向に進むことが想定されますし、認知症の症状である意欲低下や無関心にも親和性があります。
何でもいいので、興味を持って、学び続けましょう。
そこがスタートラインです。
さて、私達が本を読んだり、講座を受講したりする場合、多くの人は、それを自分の頭で再構成せず、そのままの言葉で理解しようとします。
しかし、それでは、本当に理解しているかどうか確認できません。
しかし、他人に教えようとすると、それを自分の頭で再構成・再整理をする必要があります。
そうすると、自分が何を知っていて、何を知らないか、というメタ認知が活性化し、より正確な理解を求めることになります。
そして、他人に教えるための準備と実際に他人に教える場面では、何度もその内容を思い出しています。
これは、勉強において、問題集を解くのと同じく、何度も自分の力で思い出す経験をし、記憶が定着することになります。
ただし、他人に教える環境にない場合も多いですね。
私も講師を依頼される場合以外のことについては、他人に教える機会がありません。
そのような場合には、学んだことを一人で再整理し、他人に教えるように独り言を言ってみることです。
それだけでも効果があります。
と、おすすめしても、おそらく実際に行動に移す人は少ないでしょう。
しかし、日常生活において、面倒なことをやるかやらないか、この毎日の一歩が長い目で見た場合に大きな差となってくると思います。
ぜひメルマガに登録を。
https://www.mag2.com/m/0000143169