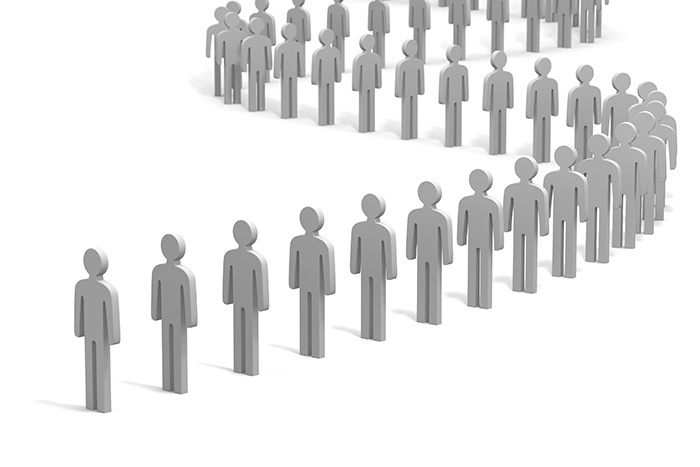フェアであることの重要性
心理学や行動経済学の本を読んだりする人には常識的な知識ですが、「最後通牒ゲーム」をご紹介します。
以下のルールで行います。
・2人のプレイヤーを提案者と応答者に分け、提案者に例えば1万円を渡す。
・提案者は両者の報酬取り分を応答者に提示する(例:6000円と4000円)。
・応答者は提案を受け入れるか拒否するか選ぶ。
・受け入れる場合:、上記の例では、応答者は4000円を受け取る。
・拒否した場合、両者はどちらも報酬は受け取れない。
このゲームは、色々な国で何度も行われているようですが、結果は、予想どおりでしょう。
経済的合理性で考えると、応答者は、いくらを提示されても受け入れた方が得、ということになります。
拒否すると、1円も受け取れなくなるためです。
しかし、8000円対2000円など、不公平感が大きい提案の場合には、応答者は拒否する確率が上昇するとのことです。
この結果から、人間は、「損得」よりも、「公平さ・公正さ」の方をより重視する、と考えられています。
神経学的には、不公平な申し出を受けたときには、脳の扁桃体や島皮質(怒りや嫌悪に関係する部位)が活性化することが判明しているそうです。
この心理は、様々な場面で登場します。
交渉の場面において、相手から見た時に「公正ではない」と判断されると、相手に得であっても、提案を拒否されることが多いです。
したがって、客観的に公正な条件よりも、「相手から見た時に公正と解釈できるか」の方が重要ということになります。
従業員に対する評価も、評価される本人から見て、「公平・公正に評価されたか」が重要となります。
子どもが複数人いるのであれば、「親が自分を公平・公正に扱ってくれたか」が重要となります。
「こっちの方が得だよ」と説得することも多いと思いますが、「こっちの方が得だし、フェアだと思うよ」と一言付け加えられる理由付けの方が、説得力が上がるでしょう。
他人を説得する時は、意見を押し付けるより、NOというための障害を取り除くことが重要です。
ぜひメルマガに登録を。
https://www.mag2.com/m/0000143169