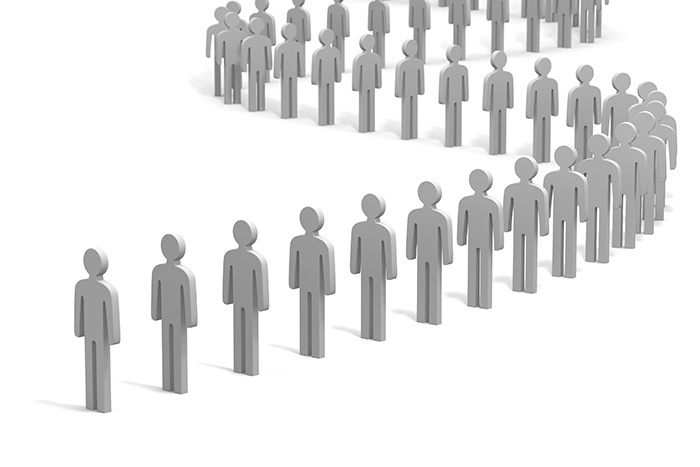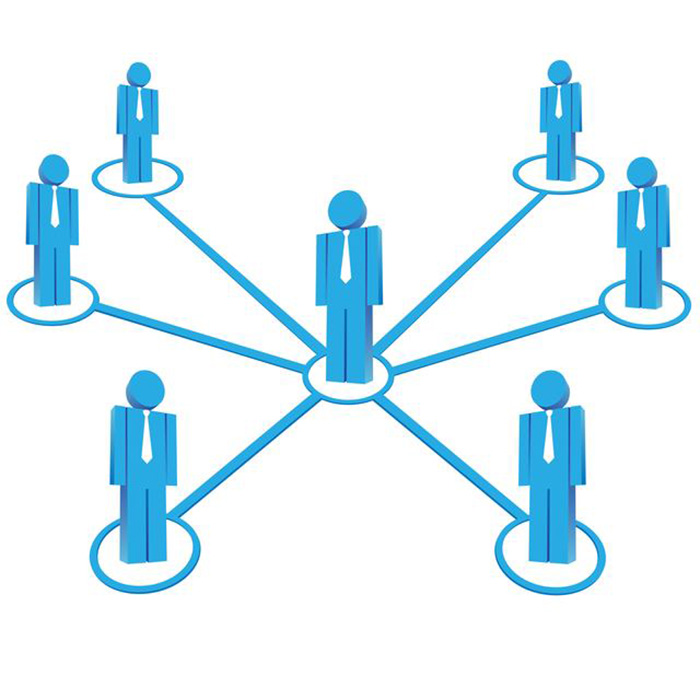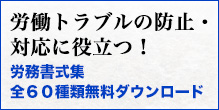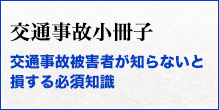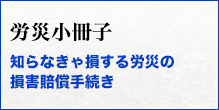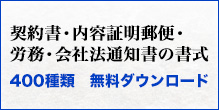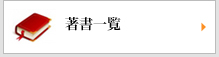自筆証書遺言の書き方

最近、年配の方の中には「終活」というものを行う人がいるようです。
これは「人生の終わりのための活動」の略で、生前に行うべきことをやっておき、終焉を見つめ準備しておくことで、今をよりよく生きようという思いがあるようです。
葬儀やお墓のこと、財産などの相続のことなど、自分のためだけでなく遺された人たちのためにもやっておくべきことがあります。
弁護士として、相続問題の相談をよく受けますが、その中に「遺言」があります。(ちなみに、法律用語では通常「いごん」と読みます)
遺言というと、映画やドラマの世界で資産家の遺言書が原因で殺人事件が起こったりする場面を思い浮かべる人もいるでしょうが、実は、普通の人でも必要となるものです。
しかし、やはり人間は「自分の死のことなど考えたくない」、「まだいいだろう。もう何年かしたら考えよう」などと、つい後回しにしがちです。
また、「うちの家族は仲がいいから遺言なんて必要ないよ」と考えている人もいるでしょう。
ところが、経験上、仲のいい普通の家族でも、いざ相続となったときにもめることが多いのです。
よく経験するのは、本人は兄弟姉妹間で争いたくないと思っていても、配偶者が「もらえるものはもらうべき。ウチだって苦しい」と言われ、泥沼の紛争に入ってゆくパターンです。
お金よりも、家や土地が残された場合、その配分でもめるケースが多いですね。
相続=争族という言葉もあるくらいです。
そこで今回は、遺言を法的に解説します。
【遺言の種類】
遺言には、死期が迫っている、一般社会から隔離されているなど特別な場合の「特別方式」と、通常の場合の「普通方式」があります。
普通方式には、さらに以下の3種類があります。
〇「自筆証書遺言」…遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名すべてを自分で記載して、捺印をするもの。
〇「公正証書遺言」…公証人に作成してもらうもの。
〇「秘密証書遺言」…遺言内容と氏名を自筆し、捺印した書面を封筒に入れ封印したものを公証人に証明してもらうもの。
私たち弁護士が遺言書の作成を依頼された場合には、「公正証書遺言」の作成を薦めるのが通常です。
遺言書の作成における弁護士の役割は、遺言者の意思を明確に遺言書に残し、かつ、死亡後の紛争を回避することです。
公正証書遺言は、公証人が作成するので、証明力が高く、紛争になりにくいからです。
でも、公正証書遺言では、余計な費用もかかるし、大事だ、ということもあるでしょう。
あるいは、たびたび書き直したい、ということもあるでしょう。
そんな時は、取り急ぎ「自筆証書遺言」を作成することになります。
ここでは、自筆証書遺言について解説していきます。
【自筆証書遺言の書き方】
自筆証書遺言として認められるための要件は、「全て自分で書く」ということです。具体的には、①遺言の内容②日付③署名を自筆し、④捺印することです。
①「遺言の内容」
必ず自筆でなければなりません。
代筆は認められません。ワープロやパソコンのワードで作成した文章は無効となります。
②「日付」
自筆で日付を書かなければなりません。「平成(西暦)〇〇年〇月〇日」と書きます。
遺言書が複数存在する場合、日付が最終のものが最終意思となり、それより前の遺言書の矛盾する部分は取り消されることになります。
③「署名」
氏名を自筆します。
必ずしも戸籍上の本名である必要はなく、従来より使用していた雅号、屋号、芸名などの通称でもよいとされています。その場合、他人との混同を避けるため住所を記載するなどして同一性を確認できるようにしておく必要があります。
万全を期すには、本名の氏と名を自筆で署名すれば安心でしょう。
④「捺印」
使用する印章は実印である必要はありません。認印でもよいとされています。
病床の人は、たとえば手の震えを抑えるために他人に介添えしてもらったり、他人に命じて押してもらってもよいとされています。
【遺言書の検認】
遺言者が亡くなった場合、遺言書の保管者(遺言者から遺言を預っている人)または、これを発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。(民法第1004条1項 遺言書の検認)
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いの上、開封しなければならないことになっています。(民法第1004条3項)
つまり、裁判所以外では開封してはいけないということです。もし開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることがあります。(民法第1005 過料)
遺言書の検認とは、有効か無効かを確定するものではなく、その外形を保全し、偽造や変造を防止し、遺言書の検証と証拠保全をするための手続き、と考えておけばよいでしょう。