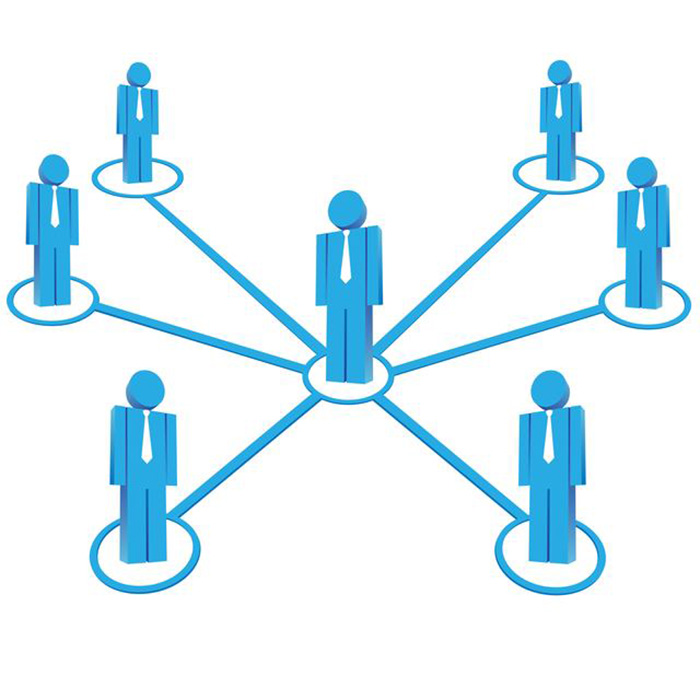ひき逃げが殺人罪に!?

自動車運転に関する事故で、ひとつのケーススタディともいえる事件が発生したので、解説しておきたいと思います。
「職務質問した警察官をひき逃げ 容疑の男逮捕」(埼玉新聞)
埼玉県川口市で、職務質問した警察官が車にひかれて重傷を負った事件で、川口署は12月17日、無職の男(31)を公務執行妨害と殺人未遂の疑いで逮捕しました。
報道によると、川口市の住宅街のT字路付近で「車が中央寄りに止まっている」との通報があり、署員2名が現場に直行。
男性巡査(30)が運転手の男に職務質問したところ、男は突然、車を急発進。転倒した巡査の脚をひき、そのまま逃走していたようです。
男は「ひき殺そうとはしていない」として容疑を否認しているということです。
まず、この事件の逮捕容疑について確認しましょう。
公務執行妨害と殺人未遂です。
「刑法」第95条(公務執行妨害)
①公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
巡査の職務質問という公務に対して、男は車を発進させて、巡査の脚をひくという「暴行」を加えて「妨害」したので、これは公務執行妨害になります。
ちなみに、職務質問を受けて、答えるのを拒否したり、ただ逃げただけでは公務執行妨害にはなりません。
なぜなら、公務執行妨害罪の要件である「暴行または脅迫」がないためです。
次に殺人未遂について考えてみましょう。
「刑法」第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。
今回は、ひかれた巡査は死んでないので、未遂罪です。
車でひき殺そうとしたが、未遂に終わった容疑ということです。
ところで、ここでひとつ疑問が出てきます。
自動車運転によって人を死傷させた場合の刑罰には、「自動車運転過失致死傷罪」(刑法211条2項)と「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)がありますが、今回はなぜこれらの容疑ではなかったのでしょうか?
報道内容からだけでは詳細はわかりませんが、おそらく「未必の故意」が疑われたのではないかと思われます。
刑法上の重要な問題のひとつに「故意」と「過失」があります。
「故意」とは、結果の発生を認識していながら、これを容認して行為をすることで、刑法においては「罪を犯す意思」のことをいいます。
一方「過失」は、結果が予測できたにもかかわらず、その予測できた結果を回避する注意や義務を怠ったことです。
では、どのような場合に故意が認められ、または過失が認められるのか?
その境界線のように存在するのが「未必の故意」です。
ある行為が犯罪の被害を生むかもしれないと予測しながら、それでもかまわないと考え、あえてその行為を行う心理状態を「未必の故意」といいます。
容疑者の男は、100%巡査を殺そうとして車を発進させたのか、たんなる不注意だったのか。
それとも、死ぬ確率は100%ではないが0%でもなく、死ぬかもしれないが「それでもかまわない」と思ってアクセルを踏んだのか、ということです。
殺人罪の未必の故意があれば、殺人罪となります。
ただ、このようなケースで「死んでも構わない」とまで思っているケースはそれほど多くありません。
そうすると、殺人罪の故意がない、ということになりそうです。
では、何罪が成立するのでしょうか?
「死んでも構わない」とは思っていなかったとしても、今回のケース、「怪我をするかもしれないが、それでも構わない」くらいには思っていたかもしれません。
そうすると、「怪我をさせる故意あるいは未必の故意」があったことになりますので、傷害罪になりそうです。
「刑法」第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ちなみに以前、ある知人で「未必の故意」を「密室の恋」だと思っていた人がいました。
危険なにおいがします……
さらには、「未筆の恋」だと思っていた人もいました。
ラブレターを書く前に終わった恋ということでしょうか……
「過失の恋」になると、人違いのようになってしまいます・・・。
それはともかく、素手の場合、殺人も傷害も大変なことですが、自動車の場合には、ちょっとアクセスを踏むだけで実現できてしまいます。
便利な反面、いつでも凶器になりうる危険なものです。
事故が予測できるにもかかわらずアクセルを踏むなど、言語道断。
冷静な判断をもってハンドルを握ることを、いつでも肝に銘じておくことが大切です。