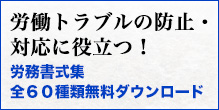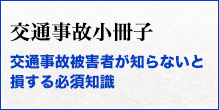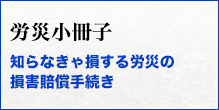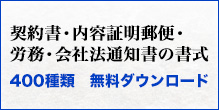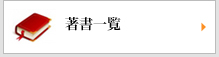-
損害賠償請求権の益金計上時期
2022年05月26日
今回は、不法行為に基づく損害賠償請求権の益金計上時期についての東京高裁平成21年2月18日判決(TAINS Z259-11144)です。
(事案)
平成16年4月に、X法人に対する税務調査で、架空外注費の損金計上が発覚した。
調査の結果、経理部長Aの詐取行為であることが判明した。
調査の結果、平成9年9月から平成16年3月までの間に、約1億9000万円詐取したことが判明したため、平成16年9月に損害賠償請求訴訟を提起し、同額の判決が確定した。
(争点)
損害賠償請求権を益金に計上すべき時期は、不法行為時か、その他の時期か?
(判決)
【原則】
本件各事業年度において詐取行為により被控訴人が受けた損失額を損金に計上すると同時に益金として損害賠償請求権の額を計上するのが原則【例外】
本件各事業年度当時の客観的状況に照らすと、通常人を基準にしても、本件損害賠償請求権の存在・内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるとすれば、当該事業年度の益金に計上しない取扱いが許される【あてはめ】
詐取行為は、経理担当取締役が本件預金口座からの払戻し及び外注先への振込み依頼について決裁する際に乙が持参した正規の振込依頼書をチェックすれば容易に発覚する。
決算期等において、会計資料として保管されていた請求書と外注費として支払った金額とを照合すれば、容易に発覚。
【結論】
通常人を基準とすると、本件各事業年度当時において、本件損害賠償請求権につき、その存在、内容等を把握できず、権利行使を期待できないような客観的状況にない。
各事業年度において益金に計上すべき。======================
以上です。
通常人を基準にして、
・本件損害賠償請求権の存在・内容等を把握し得ず、
・権利行使が期待できない
場合には、例外的に不法行為のあった時の事業年度に計上しないことができる、ということになりますが、あてはめでやや厳しめに判断されることに注意が必要です。
安易に「それは知り得なかったですね」と判断すると、誤ることがある、ということです。
なお、本件は社内の者でしたが、社外の「他の者」からの不法行為の場合には、法人税基本通達2-1-43があります。
===================
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
===================
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
総則6項最高裁R4.4.19
2022年05月05日
今回は、相続税に関して総則6項が適用された事案において、納税者が敗訴した最高裁令和4年4月19日判決をご紹介します。
すでにお読みになったもしれませんが、私の視点で解説します。
(事案)
被相続人は、平成21年1月30日、信託銀行から6億3000万円を借入、甲不動産を8億3700万円で購入した。
被相続人は、平成21年12月21日付けで共同相続人らのうちの1名から4700万円を借り入れ、同月25日付けで信託銀行から3億7800万円を借り入れた上、同日付けで本件乙不動産を代金5億5000万円で購入した。
平成24年6月17日(購入から約3年後)、94歳の被相続人の相続が開始した。
本件購入と借入がなければ、課税価格は6億円以上であった。
相続人らは、評価通達の定める方法により、本件甲不動産の価額を合計2億0004万1474円、本件乙不動産の価額を合計1億3366万4767円と評価し、課税価格の合計額は2826万1000円とされ、基礎控除の結果、相続税の総額は0円とされた。
税務署長は、総則6項を適用し、鑑定評価額に基づき、本件甲不動産の価額が合計7億5400万円、本件乙不動産の価額が合計5億1900万円として、課税価格を8億8874万9000円、相続税の総額を2億4049万8600円とする更正処分等を行った。
(判決)
(原則)
租税法における【平等原則】により、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、合理的な理由がない限り、平等原則に違反するものとして違法。(例外)
評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが【実質的な租税負担の公平に反する】というべき事情がある場合には、評価通達によらない合理的な理由がある(本件では)
本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。
そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。
そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
===================
以上です。
ポイントは、
・実質的な租税負担の公平に反する場合は、評価通達によらない合理的理由がある。
・通達評価額と鑑定評価額の差が大きいだけでは理由にならない。
・相続税額の差が大きく、かつ、関係者が相続税の軽減を知り、期待して行った場合には、実質的な租税負担の公平に反する。
ということになります。
税負担の軽減という「客観的要素」だけではなく、税負担の軽減目的と認識という「主観的要素」を判断要素に取り入れた、ということになります。
したがって、行為計算否認規定の場合と同様、税負担の軽減以外の合理的目的を有し、かつ、その証拠を残しておくことが大切となってきます。
銀行融資を受ける際に、購入目的を「相続税の軽減」と説明すると、それが稟議書に記載され、反面調査で明らかになりますので、税負担の軽減以外の目的の場合には、きちんとその目的を正しく説明しておくことが大切です。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
名義預金が否定された裁決例
2022年04月21日
今回は、課税庁による名義預金の認定が裁決により覆された事例をご紹介します。
国税不服審判所令和3年9月17日公表裁決です。
事案は、争点に絞って簡略化します。
(事案)
被相続人は、生前、「私は、平成拾参年度より以後、毎年八月中に左記の四名の者に金、○○○○円也を各々に贈与する。但し、法律により贈与額が変動した場合は、この金額を見直す。」と記載した贈与証を作成し、署名押印をしたが、預金名義である子らの署名押印はいずれもなかった。
Aは、被相続人と配偶者ではないBとの子であり、未成年者である。
Bは、Aの唯一の法定代理人親権者である。
被相続人は、母Bを通して、Aの預金口座に金員を複数回に渡り入金した。
課税庁は、母Bが本件贈与証の具体的内容を理解しておらず、被相続人の指示に従い本件預金口座に入金していたにすぎず、当該入金がAへ贈与されたものとは認識していないから、被相続人からAへの贈与は成立しておらず、本件預金口座に係る預金は被相続人の相続財産に含まれるとして、更正処分をした。
(争点)
本件預金口座に係る預金が名義預金として被相続人の相続財産に含まれるか。
※贈与は、「契約」ですので、当事者双方の意思表示の合致が必要です。
今回のケースでは、Aは未成年者ですので、母Aが法定代理人として贈与を受諾する意思表示をしたかどうかが問題となります。
(裁決)
母Bは、本件贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により本件預金口座へ毎年入金していた。
母Bは、本件預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していた。
当時、長女の唯一の親権者であった長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当である。
本件預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないから、本件預金口座に係る預金は、平成13年の口座開設当初からAに帰属するものであって、相続財産には含まれない。
======================
以上です。
相続において、相続人名義の預金が被相続人の相続財産であるという名義預金の問題が生ずることがあります。
この場合、契約書があるかないかが事実認定にとって重要となってきます。
しかし、税務では、実態で事実認定されますので、以下のこともおさえておく必要があります。
・預金通帳、印鑑を受贈者(法定代理人)が管理すること
・その預金から受贈者のための出費をすること
・通帳の届出住所を常に受贈者に一致させること
・必要な場合は贈与税の申告をすること
そして、誤った更正がされた場合には、争うことも必要と考えます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
少額減価償却資産の判定単位
2022年03月31日
今回は、少額減価償却資産の判断基準について、裁判例から検討してみたいと思います。
中小企業の場合、取得価額が30万円未満である減価償却資産について、一定の要件のもとに損金算入を認める特例があります。
この特例の適用においては、他の資産と一体として30万円以上の資産になるのか、あるいは、当該資産が独立した資産として30万円未満の資産となるのか、という論点があります。
この点、最高裁平成20年9月16日判決は、PHS電話事業において、エントランス回線利用権が一回線毎に少額減価償却資産となるのか、あるいは、PHS接続装置等と一体として30万円以上の減価償却資産となるのかが争われました。
最高裁は、減価償却資産の判定基準として、
(1)1単位として取引されているか
(2)資産としての機能を発揮して、収益の獲得に寄与するものか
の2点を検討すべきとしました。
そして、
(ア)エントランス回線は1回線でも取引の対象となり、
(イ)エントランス回線1回線に係る権利一つでもって、被上告人のPHS事業において、上記の機能を発揮することができ、収益の獲得に寄与するものということができる。
と判示しました。
したがって、減価償却資産の判定単位について迷ったら、上記基準に当てはめて検討していただくのがよろしいかと思います。
なお、上記最高裁以前にも同じ論点が争われている事例もありますが、最高裁以降は、全て上記基準によって判断されることになりますので、過去事例を上記最高裁基準にあてはめて考えていくことになります。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
破産と債務免除益
2022年03月17日
今回は、【税理士を守る会】でされた質疑応答をご紹介します。
(質問)
顧問先が債務超過に陥ったため、法的整理手続きを進めています。
顧問先が委任した弁護士は特別清算を検討しているようですが、特別清算の場合には、債務免除益が発生し、税金を払いきれない可能性があります。
破産の場合には、債務免除益を計上しなくていいと聞いたことがあります。
これは正しいのでしょうか。
正しいとすると、社長からの借入金や未払い給与についても同様でしょうか。
(回答)
特別清算については、和解型か協定型かにかかわらず、債権者との合意によって、債権が放棄される、という構成をとります。
したがって、債務が債権者側から免除されたことになり、債務免除益の計上が必要となります。
しかし、破産の場合は、債権者が債権届出をし、破産管財人が破産会社の財産で換価できた範囲内で配当を実施し、残余の債権が残ったまま破産手続が終結します。
この場合、「会社が破産宣告を受けた後破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合には、これにより会社の負担していた債務も消滅するものと解すべき」(最高裁平成15年3月14日判決(民集57巻3号286頁)、とされており、債務が消滅する時点では、すでに債務免除益が生ずべき法人が存在しないことになります。
つまり、・・・
【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読むことができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
損害賠償金と消費税
2022年02月17日
今回は、【税理士を守る会】でされた質疑応答をご紹介します。
(質問)
顧問先の社員が独立し、顧問先の顧客を奪取したことから、損害賠償を請求し、違約金を受け取りました。
そこで、この違約金が消費税基本通達5-2-5(損害賠償金)
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に
伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」に該当するかあるいは、
「但し、(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無
体財産権の権利者が収受する損害賠償金」は資産の譲渡等の対価に該当するになるか、悩んでおります。
見解をお教えください。
(回答)
通達にいう「無体財産権」の侵害に該当するかどうかは別として、資産の譲渡等の対価に該当すると考えます。
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされている趣旨は、当該損害により、心身又は資産につきマイナスが生じ、損害賠償金を受領することにより従前の状態に戻るだけであって、「担税力」が生じない、というところにあると解されます。
そうだとすると、損害賠償金であっても、本来売上や収入に替わるものであって、担税力を生ずるものであれば、資産の譲渡等の対価と解すべきとなります。
この観点から、5-2-5(1)は、・・・
【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読むことができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
【税理士向け】税と民事の時効の違い
2021年12月30日
今回は、【税理士を守る会】の質疑応答をご紹介します。
先生方の参考になるのではないか、と考えるためです。
(質問)
他社から借り入れた債務がある場合に、何年もその状態になっていて、先方からも督促がされない場合に、時効のようなものが成立して債務が消滅することはありますでしょうか?
インターネットで調べると、法人の場合は5年となっているようです。
また、この時効成立がある場合に、このタイミングで債務免除益として税務上は益金算入が必須になるという理解になりますでしょうか?
(回答)
ご指摘のように、「消滅時効」という概念があります。
法人同士の貸金債務の場合、債務の承認や督促等がなければ5年で消滅時効が完成します。
この点、租税の時効と民事上の時効は異なりますので、ご注意ください。
租税債権の徴収権は、【原則として】、法定納期限から5年間です(国税通則法72条1項)。
5年経過すれば、何らの手続きを要せず、当然に消滅します。
しかし、民事上の債権は、たとえば、消滅時効期間が5年だったとしても、5年を経過しただけでは、当然には消滅しません。
債務者側が「援用」をしない限り、債権は存在し続ける、ということになります。
「援用」の手続きとしては、内容証明郵便等で、債権者に対し、「債権は時効で消滅したので、消滅時効を援用します」と送れば完了です。
法律上は、消滅時効の援用により、起算日である「権利を行使できる時」、たとえば、支払日などに遡って消滅し、その時からなかったことになります。
しかし、税務上の処理については、・・・
【税理士を守る会】の会員の先生は、全文を読むことができます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
【税理士向け】令和4年度税制改正大綱
2021年12月16日
先週発表された令和4年度税制改正大綱で、税理士法や附帯税関連でいくつか気になるものがありました。
(1)税理士事務所の該当性の判断の見直し
税理士法基本通達40-1は、「法第40条に規定する『事務所』とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいいます。そして、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。」と規定しています。
改正では、このうち、
・設備の状況
・使用人の有無
などの物理的な事実により判断しない運用を行う、としています。
(令和5年4月1日より)
(2)懲戒と廃業
これまで懲戒処分を受けそうな時に、自主廃業して税理士資格を喪失することによって懲戒を免れる、という方法がとられてきましたが、この方法は今後取れません。
「税理士であった者」に対して「懲戒すべきであった」旨の決定がされる制度に変わるためです。
そして、この決定を受けた場合には、税理士業務の禁止の場合には、欠格事由に、税理士業務の停止の場合には、一定期間登録拒否事由に該当することになります。
(令和5年4月1日以降の違反行為に適用)
(3)懲戒処分の除籍期間
懲戒の事由があったときから10年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない、とされています。
(令和5年4月1日以降にした違反行為に適用)ということなので、当分無関係です。
(4)法人版事業承継税制
特例承継計画の提出期限は令和5年3月末でしたが、1年延長し、令和6年3月末となりました。
適用期限の令和9年12月末は延長されません。
(5)過少申告加算税等の加重
(一)税務調査において、帳簿提示提出拒否または帳簿に記載すべき売上等の金額の2分の1以上が記載されていない場合には、10%が加算されます。
(二)税務調査において、帳簿に記載すべき売上等の金額の3分の1以上が記載されていない場合には、5%が加算されます。
(6)隠蔽仮装行為があった場合の損金不算入
隠蔽仮装行為があった場合、明らかな取引及び金額など以外は損金算入が否定されます。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
一年当たり平均額法を採用した裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)
2021年09月30日
今回は、取締役の退職給与について、功績倍率法ではなく、一年当たり平均額法が採用された裁判例をご紹介します。
東京地裁令和2年3月24日判決(TAINS Z888-2350)です。
(事案)
原告会社は、肉用牛の飼育、肥育及び販売事業等を行う株式会社。
本件取締役の勤続年数は17年(争点となりましたが)。
平成19年4月~平成24年12月までの役員報酬は月額25万円。
平成25年1月11日に最終月額報酬を100万円とする遡及増額決議を行った。
支給退職給与は2億7000万円。
税務署長による更正処分は、役員退職給与の適正額は6250万0672円であり、2億0749万9328円は、不相当に高額な部分の金額に該当するとした。
(判決)
(前提)
役員退職給与の適正額の算定方法としては、平均功績倍率法が採用されるのが裁判例の傾向であることはご存じかと思いますので、この部分は省略します。
本件では、平均功績倍率法は採用せず、一年当たり平均額法を採用しています。
どのような場合に一年当たり平均額法を採用するかについて、判決では、
一年当たり平均額法は、「最終月額報酬額が当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を反映しているとはいえないなど、功績倍率を用いた方法によることが不合理であると認められる特段の事情がある場合には・・・合致する合理的な方法となり得る」としています。
そして、「功績倍率を用いた方法によることが不合理であると認められる特段の事情」については、次のように判示しています。
●本件元取締役は、遅くとも平成19年4月以降、役員報酬として月額25万円の支給を受けていたが、・・・退任の後である平成25年1月11日に、役員報酬の遡及的な追加支給がされ、その最終月額報酬額は、月額25万円の4倍に上る月額100万円とされたものである(本件遡及増額)。
●これは、専ら本件役員退職給与の額の算定根拠を整える目的で決定及び支給されたものといわざるを得ない。
その上で、一年当たり平均額法を採用し、次のように計算しました。
「1年当たり役員退職給与額の平均額及び本件役員退職給与適正額は、それぞれ、192万2538円(1円未満切上げ)、3268万2976円となり、本件役員退職給与の額2億7000万円のうち、上記の本件役員退職給与適正額を超える2億3731万7024円が不相当に高額な部分の金額となる。」
==================
ポイントしては、
・最終月額報酬額が当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を反映していると認められる場合は、役員退職給与の過大性の計算は、平均功績倍率法で行う。
・最終月額報酬額が当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を反映しているとはいえないなど、功績倍率を用いた方法によることが不合理であると認められる特段の事情がある場合には、一年当たり平均額法で計算する。
・平均功績倍率法での役員退職給与を高額にする目的で最終報酬月額のみを増額すると、上記特段の事情として認定され、平均功績倍率法が排斥される可能性が高い
ということになります。
税理士として、「最終報酬月額を増額すれば高額の退職金を出せますよ」などと、くれぐれも助言しないように注意しましょう。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
所得税で資格取得費用が経費否認された裁判例
2021年09月18日
大阪地裁令和元年10月25日判決(TAINS Z269-13330)のご紹介です。
柔道整復師の専門学校に支払った授業料が個人事業の必要経費になるかどうかが争われた事例です。
(事案)
個人で整骨院を開業する納税者が、柔道整復師養成の専門学校に通学し、その授業料等を事業所得の必要経費に算入して平成25年分及び平成26年分の所得税等の確定申告をしました。
税務署長は、本件支払額は家事上の経費に該当し、必要経費に算入されないとして、更正処分及び過少申告加算税を賦課しました。
(判決)
【判断枠組み】
●(個別対応の費用かどうか)本件支払額は、原告が免許を取得するために本件学校に対して支払った学費等の納入金であって、原告が本件各年分に行っていた事業により得る収入に直接対応する支出ではないため、事業による収入を得るため直接に要した費用(個別対応の費用)でないことは明らかである
●(期間対応の費用かどうか)ある費用が事業所得の金額の計算上、期間対応の費用に該当し、必要経費として控除されるためには、当該費用が、所得を生ずべき業務と関連し、かつ、その遂行上必要なものであることを要するものと解される
●業務との関連性及びその遂行上の必要性の有無については、
(ア)当該業務の具体的な内容、性質等を前提として、
(イ)事業者が当該費用を支出した目的、
(ウ)当該支出が、当該業務に有益なものとして収入の維持又は増加をもたらす効果の有無及び程度(その判断に当たっては、当該支出が、当該業務に係る収入の維持又は増加ではなく、むしろ所得に含まれない人的資本の価値の維持又は増加をもたらすものであるか否かも考慮すべきである。)
等の諸事情を考慮して判断することが相当である。
【当てはめ】
●原告は、本件各年当時、自らは免許を有さずに柔道整復に該当しないカイロプラクティック等を行うとともに、柔道整復師を雇用して柔道整復を行わせるという形態の事業を営んでいた
●自らが免許を取得して柔道整復を行うことで本件接骨院の経営の安定及び事業拡大を図ることを目的として本件支払額を支出したものということができる
●しかしながら、本件支払額は、本件各年当時において、前記の形態の事業による収入の維持又は増加をもたらす効果を有するものではない
●原告が本件各年後に柔道整復を業として行うことにより収入を維持又は増加させる効果を有するとしても、その事業は、原告が、施術所の開設には不要な業務独占資格である免許を自ら取得した上で柔道整復を行う点において、前記の形態の事業と大きく異なったものとなる一方で、本件支払額は、業務独占資格を獲得するという所得に含まれない人的資本の価値増加を得る効果を有するものであるということができる。
●そうすると、本件支払額は、本件各年当時における原告の所得を生ずべき業務と関連し、かつ、その遂行上必要なものであると認めることはできない。
===================
以上です。
個人事業で整骨院を営む者が、今後の業務の維持・拡大のために柔道整復師の専門学校に支払った授業料の必要経費性が否定されたものです。
業務に関連するか、といえば、関連するわけですが、裁判所は、「個別対応」、「期間対応」についてそれぞれ検討の上、これを否定しました。
うっかり必要経費に入れないように、個別の検討が必要なところだと思います。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/