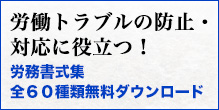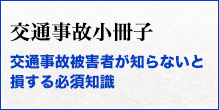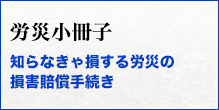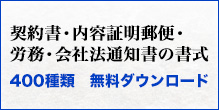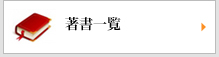-
持分会社からの利益配当の計上時期
2023年07月07日
合同会社、合名会社などの持分会社において、利益の配当を受けた時には、いつの日の属する事業年度の収益又は年の所得に計上するか、という点について解説します。
持分会社においては、定款に定めない限り、社員総会がありません。
株式会社のような決算承認手続きが定められていません。
したがって、社員総会を定款に定めていない持分会社については、社員総会で決算承認をしたとしても、法律上、その時点で決算が確定したことになりません。
そして、持分会社の社員は、持分会社に対し、いつでも利益の配当を請求することができます(会社法621条)。
この場合、利益配当請求の意思表示が会社に到達した時に具体的配当受領権が発生し、遅滞に陥ると解されています。
そうすると、権利確定主義のもとでは、社員総会と関係なく、会社に意思表示が到達した時点の属する事業年度又は年に計上することとなります。
ここまで読んで焦った先生もいらっしゃるかと思います。
しかし、国税庁「その他法令解釈に関する情報」(法人税)「 5 収益等の計上に関する通則」 2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)によると、法人が持分会社から利益の配当を受けた場合には、次に該当する事実があった時の事業年度に収益として計上する、とされています。
==============================
1)ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日
==============================
(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/06.htmつまり、課税実務では、定款に定めがない場合には、社員総会あるいは社員の過半数の同意があった日の属する事業年度で計上すればよい、ということになります。
法律解釈と課税の実務上の扱いが異なる、ということです。
上記取扱が変更になることも考えられるので、もし、株式会社と同様の扱いをしたい、ということであれば、定款に、利益の配当をしようとするときは、その都度、社員の過半数によって、
(1)配当財産の種類・帳簿価額の総額
(2)社員に対する配当の割当てに関する事項
(3)当該利益の配当が効力を生ずる日
を定めなければならない旨定めておくことをおすすめします。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
役員・従業員・親族の隠蔽仮装と重加算税
2023年03月10日
今回は、法人の役員や従業員、あるいは納税者の家族が隠蔽又は仮装をした場合に重加算税の賦課要件を満たすか、について解説します。
国税通則法第68条1項は、
(1)過少申告加算税の規定に該当する場合
(2)納税者が
(3)その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、
(4)隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた
場合に重加算税が賦課されると規定しています。
役員、従業員、家族等が隠蔽又は仮装した場合に、(2)の「納税者が」に該当するかどうか、という問題です。
この点、最高裁平成18年4月20日判決は、税理士が納税者に無断で隠ぺい又は仮装行為をした事案において、隠ぺい仮装行為を納税者「本人の行為と同視できる場合」に重加算税の賦課要件を満たすとしています。
「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月 大阪国税局 法人課税課、TAINS H250400課税処分留意点、179頁)は、以下のように記載しています。
========================
「代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。
従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる」========================
過去の事例では、以下のようになっています。
【納税者敗訴】
(1)納税者の父親
大阪地裁昭和36年8月10日判決
父親が不動産売却の代理人かつ管理の実権を持っていた。
(2)納税者(法人)の取締役
名古屋地裁平成4年12月24日判決
代表者の実弟であり、かつ常務取締役
(3)納税者(法人)の代表者の非親族の経理補助業務従業員
大阪地裁平成10年10月28日判決
・管理監督不十分
・知り得たのに放置
・代表者の遠縁で法人設立時から従業員
【納税者勝訴】
(1)納税者の弟
鳥取地裁昭和47年4月3日判決
共同経営で売上折半。弟が売上を脱漏し、仮装名義に入金の事実を納税者は知らず。
(2)共同相続人の1人
国税不服審判所昭和62年7月6日裁決
相続人の1人が被相続人及びその一族の不動産賃貸料収入等を運用した無記名定期預金を隠ぺいした事案。他の相続人(納税者)は了知していない。
このように、納税者本人の行為と同視できるかどうかについては、個別具体的事情によってきますので、重加算税賦課決定がされた場合は、慎重に検討することが重要です。
迷った時は、ご相談ください。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
課税処分に対する不服申立期間
2023年02月02日
今回は、税務調査の結果、更正等の処分がされた時の不服申立の期限について解説します。
以下は、原則的手続です。
正当な理由がある場合の例外のルールは割愛しています。
1 再調査の請求
更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、税務署長に対して再調査の請求をすることができます(国税通則法75条1項)。
2 審査請求
(1)更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、いきなり国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(同条同項)。
(2)再調査の請求を行って、再調査の決定がされた場合には、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます。
(3)再調査の請求を行ったにもかかわらず、3ヶ月を経過しても再調査決定がない場合には、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(国税通則法75条4項1号)。
3 原処分取消訴訟
(1)国税不服審判所長による裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に出訴することができます(行政事件訴訟法14条1項)。
(2)裁決があった日から1年を経過したときは、出訴できません。
(3)国税不服審判所長に対し、審査請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても裁決がないときは、出訴することができます(国税通則法115条1項1号)。
不服申立期間が経過しないようご注意ください。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
税理士法人の破産と社員税理士の責任
2023年01月27日
今回は、税理士法人の破産と社員税理士の責任について解説します。
株式会社等は、「債務超過」あるいは「支払不能」の場合に破産申立ができます。
しかし、合名会社は、「支払不能」の場合にしか破産申立ができません(破産法16条)。
そして、税理士法48条21第6項は、「破産法第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。」とされていますので、税理士法人も、「債務超過」だけでは破産できず、「支払不能」の場合のみ破産が可能です。
「支払不能」とは、支払能力がなくなったことで、本来であれば履行すべき債務を履行できなくなる状態をいいます。つまり、収入や資産がなくて返済期日の到来している債務を返せない状態のことです。
では、税理士法人が破産すると、その債務はどうなるのでしょうか。
ご承知のとおり、税理士法人の社員は、無限連帯責任を負っています。
条文としては、税理士法第48条の21は、会社法580条第1項を準用しています。
==================
会社法第580条第1項社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
==================では、退社した社員については、どうか。
次の規定も準用されています。
==================
会社法612条1 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
==================
つまり、社員税理士は、税理士法人を脱退したとしても、脱退登記後2年間は、無限連帯責任を負う、ということです。
そして、税理士法人が破産開始決定を受けると、解散します(税理士法48条の18)。
その結果、定款で「破産」または「解散」した場合は社員は脱退する旨定められていれば、脱退登記により上記の責任と同様になりますし(多くの場合はそうなると思います)、記載がなくても破産手続が終了すると法人格が消滅しますので、当然脱退となります。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
過去の申告書の閲覧サービス
2022年12月23日
今回は、過去に提出した申告書を見たい場合の閲覧サービスについてです。
新規受託をした場合に、過去の申告書がない、というケースもあると思います。
そのような場合には、過去に提出した申告書を確認する必要がある場合があります。
その場合の方法としては、
・申告書等閲覧サービス
・個人情報保護法による開示請求
の2つがあります。
今回は、申告書等閲覧サービスについてです。
閲覧申請できるのは、納税者等及びその代理人です。
・所得税及び復興特別所得税申告書
・法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
・消費税及び地方消費税申告書
・相続税申告書
・贈与税申告書
・酒税納税申告書
・間接諸税に係る申告書
・各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
・納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類
但し、相続税申告書について、他の相続人の提出した申告書を閲覧するには、当該相続人による閲覧申請あるいは委任状が必要になります。
つまり、閲覧申請をした人の該当箇所しか閲覧することはできない、ということです。
詳細は、以下をご確認ください。
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htmでは、他の相続人の提出した相続税申告を、裁判所を通して開示請求できるか、ですが、これも難しいです。
福岡高裁宮崎支部平成28年5月26日決定は、遺産分割調停事件において、相続税申告書等の文書提出命令の申立てについて、当該文書は、その記載内容が、「その提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」(民事訴訟法220条4号ロ)に該当するとして文書提出命令の申立てが却下されています。
-
質問検査拒否の刑罰の発動
2022年12月16日
今回は、質問検査拒否の刑罰が、どんな場合に発動されるのか、について裁判例をご紹介します。
質問検査は、ご承知のとおり、任意の行政調査ですが、質問検査の拒否等には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
刑罰の対象となるのは、
・不答弁
・虚偽答弁
・検査、採取、移動の禁止、封かんの実施の拒否・妨害・忌避
・物件提示又は提出の拒否
・虚偽記載記録の提示・提出
です(国税通則法128条2号、3号)。
質問検査を拒否して起訴され、無罪となった裁判例に、東京地裁昭和44年6月25日判決があります。
裁判所は、単なる不答弁ないし拒否だけでは要件を満たすとはいえず、「その質問等についての合理的な必要が認められるばかりでなく、その不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事由が認められる場合にのみ成立する」と規範を立てました。
その上で、当該事案においては、「被告人のように、一般のいわゆる白色申告者である場合には、単に帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいといわれただけで、これに応じなかったといって、ただちに不答弁ないし検査拒否として処罰の対象になるものと考えることはできない」
ポイントとしては、
・質問等についての合理的な必要が認められること
・不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事由が認められることが必要
・単なる不答弁等は処罰の対象とはならない。
・但し、質問検査拒否の他の論点である青白申告承認取消及び消費税の仕入税額控除否認に注意(帳簿書類の備え付け、記録及び保存が法律の定めるところに従って行われていない)
となります。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
贈与契約書がなくても名義預金を否定した裁決例
2022年10月14日
今回は、名義預金です。
贈与契約書がない事例において、贈与が認定され、相続財産ではないと認定された国税不服審判所令和3年9月17日裁決をご紹介します。
(事案)
請求人の亡夫(被相続人)が、被相続人の嫡出でない子(長女)に対し、毎年一定の金額を、長女の唯一の法定代理人である母を介して、長女名義の普通預金口座に、平成13年から平成24年までの間、入金した。
被相続人は、長女に対し、毎年一定額を贈与する旨の贈与証を作成したが、長女や長女の母の署名押印はなかった。
贈与証には、「私は、平成拾参年度より以後、毎年八月中に左記の四名の者に金、○○○○円也を各々に贈与する。但し、法律により贈与額が変動した場合は、この金額を見直す。」と記載されていた。
長女の母は、本件被相続人の指示に基づきM名義口座への入金を行っていただけであった旨申述しており、M名義預金の通帳をMに渡す際には、本件被相続人がMのために積み立てていた金員である旨を説明していた。
(争点)
贈与契約が成立するためには、贈与者の贈与の申込みと受贈者の受諾の意思表示が必要であるが、本件で、受贈者の受諾の意思表示があったか。
(裁決)
長女の母は、本件被相続人から本件贈与証を預かるとともに、本件被相続人の依頼により本件長女名義口座に毎年入金し、さらに長女名義預金の通帳を長女に渡すまでの間、管理していた。
本件贈与証の内容は、その理解が特別困難なものとはいえず、また、長女の母は、関連法人の経理担当として勤務していたことを併せ考えると、本件贈与証の具体的内容を理解していたとみるべきであり、そのことを前提とすると、母は、自身が手続を行っていた本件被相続人の預金口座から長女名義口座への資金移動について、本件被相続人から長女への贈与によるものであると認識していたと認めるのが相当である。
長女の母は、長女の法定代理人として、本件贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として本件預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当である。
=========================
以上です。
本件では、子への贈与が認定されましたが、課税庁から贈与を否認されました。
贈与を否認されるだけで、納税者としては、審査請求などをする苦労が増え、また、名義預金と認定されるリスクが生じる、ということです。
そして、否認された大きな理由としては、やはり、贈与証に受贈者の署名押印がない、という点です。
したがって、未成年者への贈与においては、未成年者の法定代理人の署名押印のある贈与契約書が重要である、ということがわかります。
なお、本件では、法定代理人が母親だけの事例ですが、法律上、両親がいる場合には、両親が共同して親権を行使すると定められていますので、両親の署名押印が必要となります。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
親の事業に子が参加した場合の収益の帰属
2022年08月18日
今回は、親の事業(歯科医院)に子(歯科医師)が参加した場合、収入は、親に帰属するか、それぞれに帰属するか、という論点です。
東京高裁平成3年6月6日判決(TAINS Z183-6725)です。
(事案)
原告は歯科医師であり、歯科医院を営んでいる。
原告の子であるAは、歯科医師試験に合格後、当該歯科医院にて診療に従事していた。昭和57年3月に、A名義の個人事業の開業届出書を税務署に提出した。
原告は、昭和57年および58年分の所得税について、歯科医院の総収入および総費用をAと折半して申告した。
税務調査があり、Aは独立の事業者ではなく、原告の専従者であり、医院からの事業収入は全て原告に帰属する、として更正処分及び過少申告加算税決定処分をした。
(判決)
【所得の帰属の判断】
親子が相互に協力して一個の事業を営んでいる場合における所得の帰属者が誰であるかは、その収入が何人の勤労によるものであるかではなく、何人の収入に帰したかで判断されるべき問題であつて、ある事業による収入は、その経営主体であるものに帰したものと解すべきであり(最高裁昭和37.3.16第2小法廷判決、裁判集民事59号393頁参照)
従来父親が単独で経営していた事業に新たにその子が加わつた場合においては、特段の事情のない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入つたものと解するのが相当である。
【考慮要素】
原告夫婦とA夫婦及びその子は、同一建物の1階と2階に住み分けており、独立の出入り口はないなどから、Aは全く別個の世帯とは認められない。
Aが開業にあたり必要とした医療器具、医院改装の費用は原告の負担であり、売買契約等の契約者も原告であり、借入にあたり、原告所有土地建物に担保設定医院の経理上Aと原告の収支が区分されていない
同医院の収入が昭和56年から飛躍的に増大していることが認められるとはいえ、本件で問題になつている昭和56年から同58年にかけての医院の実態は、Aの医師としての経験が新しく、かつ短かいことから言つても、原告の長年の医師としての経験に対する信用力のもとで経営されていたとみるのが相当であり、したがつて、医院の経営に支配的影響力を有しているのは原告であると認定するのが相当である。
原告とAの診療方法及び患者が別であり、いずれの診療による収入か区別することも可能であるとしても、原告が医院の経営主体である以上、その経営による本件収入は、原告に帰するものというべきである。
==================
以上です。
子が歯科医師という資格を有し、治療を担当していたとしても、父親が全体の経営主体であり、収入金額すべてが父親の収入になる、という結論です。
親の事業に子が参加した場合には
(原則)
従来父親が単独で経営していた事業に新たにその子が加わつた場合においては、特段の事情のない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入つたものと解する
その上で、例外として、「特段の事情」を検討する、という順番になります。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
【税理士向け】母親名義の食堂で収益の帰属が争われた事例
2022年07月08日
今回は、母親名義の食堂の収益について、母親に帰属するか、請求人(子)に帰属するか、について判断した国税不服審判所平成3年11月14日裁決(TAINS F0-1-1153)をご紹介します。
(事案)
請求人は、昭和61年分ないし昭和63年分の所得税について、給与所得があったとして確定申告した。
課税庁は、食堂の収益は請求人(子)に帰属するため、請求人の所得は給与所得ではなく、事業所得に当たるとして、所得税の更正及び過少申告加算税の各賦課決定をした。
(裁決)
以下の事実を認定して、母親名義の食堂の収益は、請求人(子)に帰属するとしました。
・本件食堂の営業許可名義は、母親名義である。
・食堂の収益は母親が事業所得として申告していた。
・食堂の建物は母親名義であるが、改築費用2573万円については、請求人が借入をして工事費用を負担した。
・上記借入金の返済は、食堂の収入金で行われた。
・請求人は約20年食堂の営業に従事し、仕入れ交渉、契約、材料の調理など営業活動で主要な役割を果たしており、母親は高齢で日常的に営業活動に従事していなかった。
・売上金の管理は請求人の名義で行われていた。
===================
本件は、もともと母親が経営していた食堂について、明確に事業の承継が行われたことがないにもかかわらず、実態から、請求人を経営者と認定したものです。
実質所得者課税の原則の見解には、法律的帰属説と経済的帰属説がありますが、多くの裁判例では、法律的帰属説で判断されています。
法律的帰属説は、形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきとされています。
本件のような事例では、上記のように、様々な点を検討しないと適切に事実認定ができません。
以下のような事実関係を確認する必要があります。
・建物は誰の名義で所有又は賃借されているか
・売上金の管理は誰が行っているか
・仕入れ等の交渉、契約は誰が行っているか
・経営方針、人事等の決定は誰が行っているか
・重要な設備は誰が費用負担をしているか
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/
-
分掌変更退職給与が否認された裁判例・東京地裁平成29年1月12日判決
2022年06月02日
今回は、分掌変更退職給与が認められなかった裁判例をご紹介します。
東京地裁平成29年1月12日判決(TAINS Z267-12952)、控訴棄却、上告棄却です。
(事案)
乙は、原告会社において平成16年5月28日から平成23年5月30日まで代表取締役の職にいた。
乙は、平成23年5月30日に取締役に再任されたが、甲が代表取締役に選任され、乙は代表取締役を退任した。
乙の月額報酬は、代表取締役を退任する前の205万円から約3分の1に相当する70万円に引き下げられた。
原告は、乙の退職慰労金を5609万6610円とする旨の決議をし、損金に参入した。
後日の税務調査により指摘を受け、原告は、修正申告をしたが、その後、本件退職慰労金は損金に参入されるべきであるとして更正の請求をした。
税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
(判決)
役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的には退職したと同様の事情にあると認められるときは、その分掌変更等の時に退職給与として支給される金員も、従前の役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する限りにおいて、退職給与に該当する。
その上で、判決では、退職の事実を否定するにあたり、次の事実を認定しています。
●乙は、原告の代表取締役を退任した後も、常勤の相談役として毎日出社をし、退任前と同じ代表取締役の執務室の席において執務をしていた
●甲の席は乙の席の隣に設けられ、乙と甲が共同して原告の経営に当たる執務環境が整えられていた
●代表者の甲は、原告の売上げや粗利、従業員の成績の管理、棚卸し、従業員からの報告事項、夏季賞与の査定やその支払のための借入れ、冬季賞与の査定、マシニングの管理や設置などについて、案件ごとに乙に確認を求め、その助言に従って業務を実施するなどしていた
●税務調査において、代表取締役を退任した後も退任前と同様の業務を継続しており、甲に対し引継ぎとして仕事を教えている旨述べている
●代表取締役を退任した後も、代表者会議への出席を継続し、出席をしなくなった営業会議及び合同会議についても、各会議の議事録に甲が決裁印を押した後のものを確認した上で「相談役」欄に押印していた
●10万円を超える支出について必要となる決裁のための稟議書についても、原則として甲が決裁欄に押印した後に「相談役」欄に押印をしていた。
●乙は、原告の資金調達等のため、多数回にわたり、単独でE銀行結城支店の担当者との面談や交渉をしており、同銀行の担当者も、原告の交渉窓口で原告の実権を有するのは乙であると認識し、交渉等のために原告を訪問するに当たり、乙に対し面談の約束を取り付けていた
(結論)
乙は、原告の代表取締役を退任した後も、引き続き相談役として原告の経営判断に関与し、対内的にも対外的にも原告の経営上主要な地位を占めていたものと認められるから、甲が代表取締役に就任したことにより乙の業務の負担が軽減されたといえるとしても、本件金員の支給及び退職金勘定への計上の当時、役員としての地位又は職務の内容が激変して実質的には退職したと同様の事情にあったとは認められない。
=====================
以上です。
今回の判決で指摘された内容から、顧問先への助言で参考になるポイントは、以下です。
・毎日出勤しない
・代表取締役の時の執務室は使わない
・現代表取締役と同列とみなされる机の配置にしない
・経営上の重要な意志決定に関与しない
・人事に関与しない
・経営上の重要な会議に参加しない
・議事録を決裁しない
・支出に関し、決裁しない
・金融機関などとの交渉に関与しない
なお、顧問先に助言をしたら、助言をしたことを証拠化しておくことをお忘れなく。
「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/