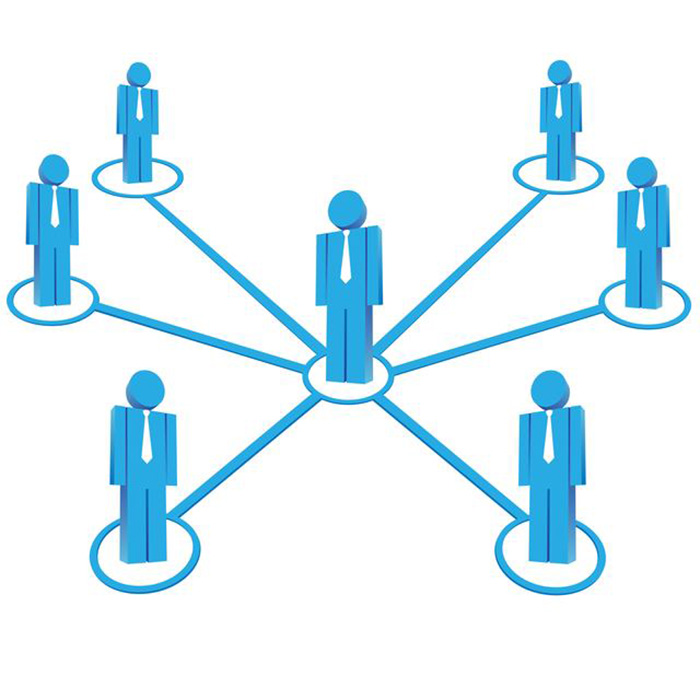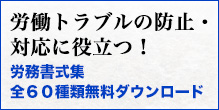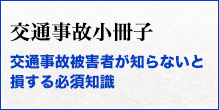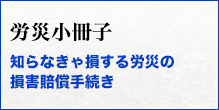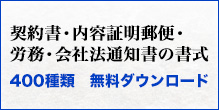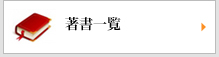税理士が損害賠償請求を防ぐ方法

目次
なぜ、税理士は、訴えられやすいのか?

税理士が関与先から損害賠償請求を受ける場面を考えてみたい。
多くの場合は、税務申告をした後、関与先が税務調査を受け、修正申告が必要となったり、更正処分を受けた場合、追加の納税が発生し、あわせて延滞税や加算税などの納付が必要となってくる。
関与先からしてみると、正しい税務申告をしていれば延滞税や加算税などは支払う必要はないわけで、ミスがあったために損害を被った、という意識になる。
そして、税務申告は税のプロである税理士に依頼して報酬を支払っているのであるから、税理士のミスによって、会社が損害を被った、という論理になる。
そこで、その損害を税理士に支払ってもらいたい、ということで、税理士に対する損害賠償請求に発展する。
もう一つ多いパターンは、関与先の代替わりなどで社長が交代し、あわせて顧問税理士を変更する、ということがある。
この場合、交替した税理士は、過去の会計帳簿や税務申告書などを検討するのが通常であるが、その過程で、過去に行った税務申告のミスが発見される場合がある。
そして、税理士がそれを会社に報告すると、従前の税理士に損害賠償しよう、ということになる場合がある。
そして、このようにして税理士に対する損害賠償請求をしよう、となった場合に、税理士は訴えられやすい業務の性質を持っている。
というのは、損害賠償請求というのは、「いくらの損害を被ったから、その損害を賠償せよ」という請求であるが、その損害額を算定するのが容易では場合も多い。たとえば、他人を殴って怪我をさせた場合、その損害はいくらか、というのは精神的な慰謝料なども含まれてきて、一応の相場はあるにしてもなかなか一義的に決まりづらい。
しかし、税理士の損害賠償は、不要な税を納付せざるを得なくなったことが損害になるので、損害額が容易に計算できてしまう、という要因がある。
また、税理士のミスは、税法や通達などに反した税務処理をした場合に起こるものであるが、課税要件はある程度税法や通達、Q&Aなどで明確になっているので、訴える方としては過失を立証しやすい、という要因がある。
このようなことから、税理士としては、関与先からいつ損害賠償請求を受けるかわからい状態に置かれていることになる。
税理士に対する損害賠償請求するときの法律構成は、委任契約の債務不履行にも基づく損害賠償請求か不法行為に基づく損害賠償請求がなされるのが通常です。
そして、債務不履行に基づく損害賠償請求の時効は10年、不法行為に基づく損害賠償請求の時効は損害等を知った時から3年ということで、業務が終了しても、10年間は損害賠償請求を受ける可能性があるという不安定な地位に置かれることになる。
なお、2020年4月1日以降に債務不履行に基づく損害賠償債務が発生した場合には、次のようになります。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
したがって、税理士としては、関与先から損害賠償請求を受けないような対策を講じておかなければ安心して業務に専念することができないのではないだろうか。
税理士の注意義務の程度はどの程度か?
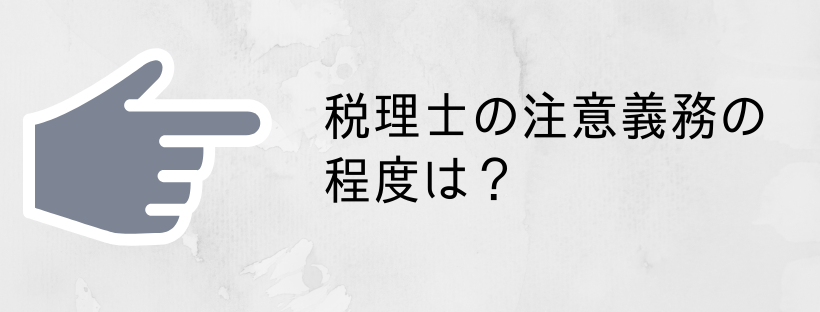
税理士と関与先との契約は、法的には委任契約とされている(最高裁昭和58年9月20日判決)。税理士がミスをした時は、委任契約の受任者としての義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生する場合と、税理士としての注意義務に違反したとして、不法行為に基づく損害賠償責任が発生する場合がある。
そして、税理士は、「委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」(東京地裁平成22年12月8日判決)とされており、注意義務の程度が重いことに注意が必要である。
具体的には、過去の裁判例によると、税理士が抗弁として、「委任者の指示に従って申告書を作成したのであるから過失はない」と主張したのに対し、裁判所は、「委任者の指示に不適切な点がある時は指摘して是正する義務がある」と判断し、税理士が抗弁として、「労務賃金の勘定科目で計上されたものが、人件費か外注費かを委任者に確認したところ、外注費であり課税対象であるとの回答を得たのでその通り申告した」と主張したのに対し、裁判所は、「委任者の回答を鵜呑みにせず、税務上の判断は税理士がすべき」と判断した事例があり、裁判所が、税理士の注意義務を高度なものと認識していることがわかる。
税理士職業賠償責任保険は万全か?

関与先から税理士に対する損害賠償請求に対する備えとしては、税理士職業賠償責任保険(以下、「税賠保険」という)がある。
しかし、税賠保険は、税理士が負担する損害賠償責任を全て補填するものではない。
まず、税賠保険で保障される「税理士業務」は、税理士が行う全ての業務ではない。税賠保険でいう「税理士業務」とは、税理士法で定める税理士業務から、付随する社労士業務などを除いた業務である。したがって、税理士法に定めていない財務や経営、医療法人に対するコンサルタント業務、相続における税務以外の助言業務などは、税賠保険の対象に含まれない。
また、保険金が支払われない免責事項として、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税、利子税等に相当する賠償額が定められている。税理士に対する損害賠償請求がされる場合には、多くの場合、加算税や延滞税が課されることを考えると、税賠保険は、税理士に対する損害賠償請求に対する備えとして万全とは言えない。
だからといって、税賠保険が不要ということではない。関与先から損害賠償請求がされた場合、税賠保険から一部でも支払われるのであれば解決がしやすい事例もあるので、加入していない税理士は加入を検討した方がよいと思う。
たとえば、株式会社日税連保険サービス作成「税理士職業賠償責任保険事故事例(2017年7月1日〜2018年6月30日)を見ると、次のような事例で税賠保険金が支払われている。
①「消費税課税事業者選択届出書」提出失念により還付不能消費税額が生じた事例
②個別対応方式・一括比例対応方式の選択誤りにより過大納付税額が生じた事例
③遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書提出を失念した事例
④期限後申告となったため住宅取得資金に係る贈与の特例が適用できなかった事例
⑤交際費等の損金算入限度額の選択を誤ったため過大納付となった事例
⑥株式の譲渡所得の計算における概算取得費・実際の取得費の有利不利判断誤りにより過大納付になった事例
⑦輸出免税の判断を誤り簡易課税制度を選択したため還付不能消費税額が発生した事例
⑧相続税申告期限前に対象宅地を譲渡したため、小規模宅地の特例の適用ができなくなった事例
⑨居住用財産の譲渡所得に係る特別控除を適用した結果、住宅借入金等特別控除ができなくなり過大納付となった事例
⑩【事前税務相談】適用になる仕入税額控除計算方式についての助言誤りによって過大納付税額が発生した事例
なぜ、契約書で損害賠償を防ぐことができるのか?

では、どうすれば、税理士は関与先からの損害賠償を防ぐことができるのであろうか?
もちろん、自分がミスをした場合には、それによって関与先が被った損害を賠償するのが法律上の原則である。
しかし、実際には、「言った、言わない」と議論になったり、税理士か関与先かどちらの責任か微妙な事案があったり、契約書をきちんとして、かつ、証拠化の努力をしておきさえすれば回避できた損害賠償も少なくないように思われる。
したがって、当職としては、税理士が業務を行う際には、ぜひ関与先との間できちんと契約書を締結することを勧める次第である。かといって、どんな契約書でもよい、というわけではなない。その契約書の条項が重要である。
さて、税理士が関与先と契約書を締結する場合、何を目的として締結しているであろうか。
おそらくは、①業務の範囲を明確にする、②報酬を取り決める、の2点であると思われる。
しかし、税理士が関与先と契約書を締結する目的として、③関与先からの損害賠償請求に備える、という点があることを指摘したい。
契約書は、税理士と関与先の法的な関係を規律するものである。税理士にどのような権利と義務があり、関与先にどのような権利と義務があるのか、を記載する。
その記載内容によって、関与先から税理士に対する損害賠償請求という法的権利が成立するかどうかが影響を受けることになる。
税理士が関与先からの損害賠償請求に備えるという観点からの重要な条項は、①業務の範囲、②資料の提供などの責任分担、③税理士の説明助言義務、④損害賠償額の制限規定、⑤税理士からいつでも中途解約できる条項、などである。
これらを契約書に記載することによって、具体的な事案によって税理士に損害賠償責任が発生するか、しないかの判断基準として作用することになる。
また、契約書は、税理士と関与先の関係が続く間、頻繁に書き換えられるものではない。委任契約が成立する際に双方が記名捺印して契約内容が確定すると、その後は参照されることは少ないし、契約書の条項が変更されるのは、委任業務の範囲が変更になるか、報酬額が変更になるか、あるいはマイナンバー法の施行など、法改正があるような場合に限定されるのが通常である。したがって、契約開始時に、契約書をしっかり作成しておけば良い、という意味で、税理士にとっても負担の少ない損害賠償請求への備え、ということができるであろう。
では、以下に、契約書にどのような条項を規定しておくべきか、について検討する。
業務の範囲は、どう記載すべきか?
「業務の範囲」というのは、税理士が、①誰の、②どの範囲の事務について、受任業務を行う義務があり、また、どの業務を行う義務がないか、を明確にすることである。
この業務の範囲を明確にすることにより、契約書に記載されていない業務について、税理士に対する損害賠償請求を回避することが可能になる。
もし、契約書で業務範囲が不明確な場合には、関与先から、「それも含めて税理士に依頼しました」と主張される可能性があるからである。
「業務の範囲」の「誰の」という点は、特にグループ会社がある場合に問題となる。
グループ会社の1社と契約書を締結していた税理士が、契約書を締結していない関連会社に対して税務上の助言をしたところ、想定外の法人税が課税されたとして、損害賠償を請求された事例で、東京地裁平成12年6月23日判決は、契約書を締結していない関連会社との顧問契約も成立していたと認定し、税理士に対する損害賠償請求を認めた。
契約書が締結されていないのであるから、契約書に規定された税理士を守るための条項は適用されない。したがって、グループ会社の場合、業務を行う以上は、必ず1社毎に契約書を締結した方がよい。
次に「どの範囲の業務を行う義務があり、また、どの業務を行う義務がないか」についてであるが、業務の範囲を明確にすることは、税理士の義務を限定することにつながる。依頼された業務の範囲については、書面で明確にしおかないと、関与先が認識している業務範囲と、税理士が認識している業務範囲が異なっている場合がある。そうなると、トラブルに発展しやすくなる。
過去の判例で、税理士に節税指導義務があるかどうかが争われた事案で、税理士の節税指導義務を認めたものに、東京地裁平成10年9月18日判決、東京地裁平成27年5月28日判決などがある。
反対に、税理士の節税指導義務を否定したものに、東京地裁平成24年3月30日判決があるが、この税理士の節税指導義務を否定した判決で重視されたのは、契約書の委任業務の記載において、節税指導義務が含まれないと解釈されたことである。
契約書において委任業務の範囲を明確にしていない場合には、税理士が業務として認識していない範囲にまで受任者としての義務が拡大して解釈される可能性がある。
したがって、契約書において、委任業務の範囲を明確に記載することによって、本来想定していない業務での損害賠償請求を防止することが可能となる。
その意味で、税理士が業務を行う際には、必ず契約書を締結し、かつ、契約書において業務を明確に規定しておく必要がある。
資料の提供などの責任分担はどう記載すべきか?
前述の税理士の節税指導義務を否定した東京地裁平成24年3月30日判決において、節税指導義務を否定した理由の一つとして指摘された契約条項の1つに、「委任事務の遂行に必要な資料等を提供する責任は依頼者にある」という趣旨の文言があった。
これは、関与先が必要な資料等を提供する責任があるのか、あるいは、税理士が必要な資料の有無を確認し、関与先に提出させる責任があるのか、という点に関係する。
もし、税理士に責任がある、ということになると、税理士は、あらゆる事態を想定して関与先に質問し、資料の有無を確認して事実を確定する義務がある、と解釈される可能性がある。しかし、それは悪魔の義務を課すものである。
したがって、上記規定を入れておくことと、「依頼者の資料提供が不十分であることに起因する依頼者の損害については、税理士は損害賠償責任を負担しない」という趣旨の規定を入れておくことが望ましい。
税理士の説明助言義務をどう立証するか?
税理士は、関与先に対して関連税法及び実務に関して、有効な情報を提供し、関与先が適切に判断できるように説明及び助言をしなければならない、という助言指導義務があるとされている。
そして、この助言指導義務を怠ったことにより、関与先に損害が発生したときは、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負担する。
税理士が関与先に対し、必要な助言指導をすべきことは当然のことである。必要な助言指導を怠り、それによって関与先に損害が発生した場合は、その損害を賠償する責任がある。
しかし、ここで問題となるのは、税理士が関与先に助言指導したことをどうやって証明するか、という点である。
過去の裁判では、税理士が「助言した」と主張し、関与先が「助言されていない」と主張して争われている例がある。
この場合、「助言した」という書類その他の客観的証拠がなければ、証明方法は、尋問によるほかない。
そうすると、いわゆる「言った、言わない」の争いがそれぞれの本人尋問あるいは証人尋問でなされることになる。
その結果、どうなるかというと、「助言した」という客観的な資料がない以上、「助言したとは認められない」、つまり、「助言義務を怠った」と認定されることが多いと思われる。
したがって、税理士は、関与先に対して助言すべき事項に関しては、可能な限り証拠を残しておくことが必要となる。
たとえば、不動産の取得譲渡や多額の設備投資などがあると、消費税の処理に影響が出る場合がある。
したがって、それらが予定される時は、税理士は消費税の申告にあたって、関与先から報告してもらうことが必要となる。
もし、関与先から税理士に報告することなしに消費税の確定申告がなされた後に、多額の設備投資が発覚し、異なる処理をしていれば消費税の税額が低くなっていた、という場合で考えてみる。
この場合、関与先が「税理士があらかじめ説明しておいてくれれば、設備投資について事前に相談したはずだ。税理士に助言指導義務違反がある」と言われる可能性がある。
消費税の確定申告に影響が出るいくつかの場合には報告してくれるように事前に説明していた場合でも、関与先は忘れている可能性がある。その場合には、「説明されていない」と主張されることになり、税理士の方で、「説明した」ことを立証する必要に迫られる。
したがって、このような説明は、事前にしておくべきであるし、説明したことを証拠に残しておく必要がある。
その一つの方法として、契約書に「次の事態が判明した時は、依頼者は税理士に対して報告を行うものとし、当該報告がなかった場合には、税理士は、これがないものとして委任事務を処理することができる」と規定し、その後に、消費税額に影響が出るような事態を列記しておく、というものがある。
また、相続税の申告において、相続税の納税ができずに期限を徒過し、延滞税等が発生した事例において、相続税の納付の期限を説明し、納付が可能であるかどうかを確認して、納付できない場合には、延納許可申請をするかどうかについて相続人に意思確認する義務がある、とした判例がある(東京高裁平成7年6月19日判決)。
これも、相続税の申告業務の委任を受けた時には、納付期限が判明しているわけであるから、契約書の特記事項などに「相続税の納付期限は、平成●年●月●日です。納付ができない場合には、延納許可申請の手続により、後日の納付や物納許可申請により相続により取得した財産での納付が認められる場合がありますので、平成●年●月●日までにご相談くさださい」と記載しておく方法が考えられる。
契約書に記載しないならば、説明書面を用意して説明した上で、説明を受けた旨の署名捺印をもらっておいてもよい。
こうしておけば、「説明したこと」および「報告する責任は依頼者にある」ということが契約書に規定されることになる。
書面にするのが難しい場合でも、FAXなりメールなりで証拠化しておいた方がよい。
契約書で損害賠償責任を制限できるか?
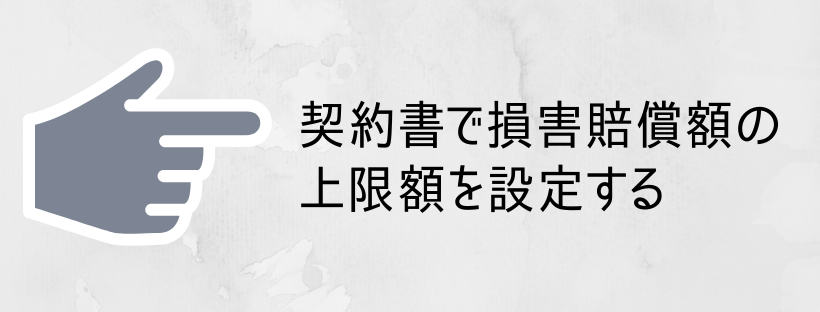
税理士の故意または過失によって、関与先に損害を与えた時には税理士に損害賠償責任が発生する。
では、この損害賠償責任を契約書によって制限することは可能であろうか。この点については、2つの論点がある。
一つは、損害賠償責任の発生自体を制限することが可能か、という点であり、もう一つは、損害賠償責任は発生するが、その金額を制限することができるか、という点である。
損害賠償責任の発生自体を制限する条項とは、たとえば、「税理士は、債務不履行又は不法行為により依頼者に損害を与えた時は、故意または重過失があった場合に限り、損害賠償責任を負担する」というような条項である。
損害賠償責任が発生する主観的要件を、故意または重過失がある場合に限定して、軽過失による場合は免責とする条項である。
この条項の有効性を規制するものとして、消費者契約法がある。この法律は、消費者と事業者との契約を規制する法律であり、税理士と消費者との契約もこの法律で規制される。法人税や消費税の申告代理業務を受任する場合は、相手は法人であろうと個人であろうと、消費者から依頼を受けるものではないから、消費者契約法の規制の対象外となる。しかし、相続税の確定申告業務を受任するような場合には、消費者契約法の規制が及ぶことになるため、消費者契約法の適用がある。
消費者契約法は、消費者の利益の擁護を図ることを目的とし、次の契約条項を無効とする。
①債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
②債務不履行で故意または重過失で消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
③不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
④不法行為で故意または重過失で消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
したがって、相続税の申告業務を受任したような場合に、契約書に賠償責任が一切発生しないというような条項や、故意または重過失の場合に賠償額の上限を設けるような条項を記載している場合には、その条項が無効になる。
相続税の申告業務などで、消費者と契約書を締結する時には、上記の規定によって無効とならないような条項に工夫する必要がある。
消費者契約法の適用対象外である、法人との契約においても、損害賠償責任の発生を制限する条項が規制される場合がある。税理士の委任契約書における損害賠償制限条項を無効と判断した裁判例は見当たらないが、準委任契約と解釈されているシステム開発契約における損害賠償責任条項が無効とされ、あるいは制限的に解釈された事例が参考となる。
東京地裁平成26年1月23日判決の事例では、業務委託基本契約に、「乙が委託業務に関連して,乙又は乙の技術者の故意又は過失により,甲若しくは甲の顧客又はその他の第三者に損害を及ぼした時は,乙はその損害について,甲若しくは甲の顧客又はその他の第三者に対し賠償の責を負うものとする。(1項)前項の場合,乙は個別契約に定める契約金額の範囲内において損害賠償を支払うものとする。(2項)」という規定があった。
この事例で、判決は、損害賠償額を制限する2項の規定は、「故意又は重過失がある場合には適用されない」と判断した。したがって、税理士の契約書において、損害賠償額の上限を設ける条項を規定しても、「故意又は重過失がある場合には適用されない」と判断される可能性がある。
東京地裁平成13年9月28日判決の事例では、開発業務等委託契約に、「被告の責めに帰すべき事由により、被告の債務を履行できなかった場合には、原告は被告に対し、委託金額を上限として損害賠償を請求することができる。」という規定があった。
そして、この条項で指摘された損害賠償額の上限となる委託金額は500万円であったところ、委託者に1478万4279円の損害が発生したという事案である。この事例で、判決は、損害賠償の上限を500万円とすることは、低廉にすぎ、「信義公平の原則に反する」と判断した。
このような判例が存在することから考えると、税理士の損害賠償責任を制限する条項を安易に規定するとその条項が無効になってしまう可能性があるから、損害賠償の制限条項は慎重に規定すべきであり、かつ、完全に有効になる、とは断言できない。
しかし、そうであっても、関与先から税理士に対する損害賠償請求を制限する上では極めて重要な規定であることを指摘しておきたい。
無償・好意の場合には損害賠償責任を負担しないか?
税理士が全ての場合に契約書を締結し、報酬を取り決めて業務を開始できれば良いが、人的関係や高度の責任を負担しきれないような場合に、無報酬にして、好意で税務に関する業務を行う場合が想定される。このような場合には、無報酬で好意であるから、わざわざ契約書を締結しないと思われる。
この場合、税理士がミスをした場合であっても、損害賠償責任を負担しないか。
東京高裁平成7年6月19日判決の事例は、税理士が、無報酬かつ好意で相続税の修正申告手続を行ったが、延納について説明しなかったので、納税できず、延滞税等の納税を余儀なくされた、として損害賠償請求された事例である。
この事例で、判決は、「税理士がその業務に関する委任状を徴求したことは、その委任状に記載の委任事項についての業務を受任したものというべきである」「報酬の約束の有無は、委任契約の成立を左右するものとはいえない」と判断し、税理士に対する損害賠償を命じた。
したがって、税理士としての損害賠償責任が発生する以上、無報酬であっても業務を行う場合には契約書を締結した方がよい。
なお、税理士の顧問契約は、法律上、委任契約とされていますが、民法648条は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」とされています。
つまり、委任契約は、無償が原則である、ということです。
違法な業務を依頼されたら?
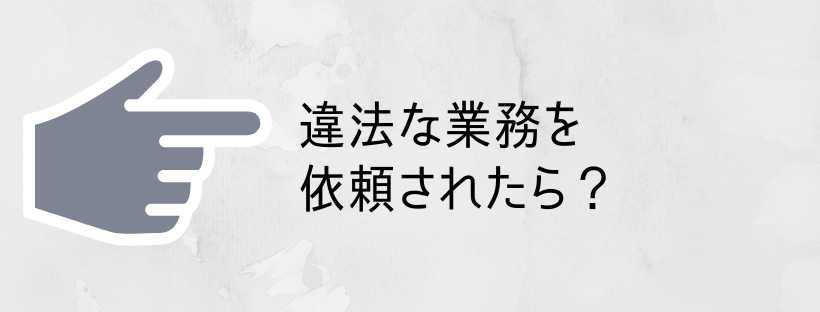
関与先の中には、稀に税理士に対して、脱税の指南を求めたり、資料を提出せずに「このように処理してください」と、適正な納税義務の実現に反するような依頼をしてくる場合がある。
このような場合、税理士としては、税法およびリスクを十分説明して、適正な納税義務の実現を果たすよう説得することが求められる。
しかし、それでも翻意しない場合には、とりあえず不十分な内容で税務申告書を作成し、申告代理をするか、あるいは契約を解約するか、の決断を迫られることになる。
過去の裁判例で、税理士が所得税確定申告にあたって、依頼人に対し、申告書作成に必要な原始資料の提出を求めたが、これを拒否し、依頼人の指示する不適法な方法で確定申告をするよう要請され、その旨申告したが、その際、重加算税などの説明をしなかったため、納税を余儀なくされたとして、損害賠償され、それが認められた事案がある。
この事案で、過失相殺はしたものの、税理士に対して一部損害賠償責任を認めた(前橋地裁平成14年12月6日判決)。
また、税理士法第45条は、税理士の懲戒について規定しているが、同条第1項は、「財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。」とし、故意の脱税等の行為に対する懲戒を規定し、第2項は、「財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。」として、過失による脱税等の行為に対する懲戒を規定している。
したがって、税理士が違法な納税行為に関与するときは、損害賠償責任だけでなく、懲戒リスクもあることを認識すべきである。
結論
以上論じたところから、税理士が関与先と契約書を結ぶ際の留意点をまとめてみる。
(1)税理士が業務を行う以上、たとえ無報酬であっても契約書を締結した方がよい。
(2)グループ会社の場合には、1社毎に契約書を締結することとし、法人と個人の別がある場合には、それぞれに契約書を締結した方がよい。
(3)契約書では、「どの業務を行い、どの業務は業務範囲に含まれないか」を明確に記載すべきである。
(4)契約書では、「資料の提供は、税理士と依頼者のどちらが責任を負うのか」を明確にした方がよい。
(5)税理士の説明助言義務が想定される事項については、あらかじめ契約書や別途書面に記載して交付することにより、説明助言義務を果たしてしまうことを検討すべきである。
(6)損害賠償額の制限規定を規定する場合には、過去の判例を踏まえて無効とならないよう規定すべきである。
(7)契約期間中であっても、税理士からいつでも契約を解約できるようにしておいた方がよい。
以上の留意点は、何も税理士の責任回避を目的とするものではない。過去の裁判例を読むと、税理士の責任を広範に認めるものが多い。
しかし、税理士が無制限に損害賠償責任を負担するときは、いきおい税理士の助言指導や税務処理は決して間違いのない極めて保守的な判断に傾く可能性がある。税法や通達を読んでも解釈の余地がある場合は多く、このような時、後日の税務調査で指摘され、修正申告を余儀なくされた時に、税理士が損害賠償責任を負担する、というのでは、税理士は、否認の余地がないような保守的な助言指導や税務処理に傾く可能性がある。
税理士の損害賠償責任を一定限度制限することにより、解釈の余地がある処理において、もっとも関与先にとってメリットのある助言指導や税務処理が可能となると考える。
また、税理士は税務の専門家であるから、税務処理が問題となった時は、関与先から「税理士に全て任せているのだから、税理士の責任だ」と言われやすい。しかし、関与先から報告を受けたり、資料を提供してもらわなければ税理士も容易に知り得ないことも多い。
したがって、税理士と関与先の責任の分担について、契約書で定めておくことは、税理士の責任を無制限に広げず、合理的な範囲にとどめることに役立つものである。
したがって、税理士が、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るためにも、業務を行う場合には、必ず契約書を締結することとし、その契約書の内容も十分吟味することを期待するものである。
税理士先生からの税賠相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。
「税理士を守る会」は、こちらから。
https://myhoumu.jp/zeiprotect/
もっと詳しく知りたい方は、こちらの書籍も参考にしてください。
「税務のわかる弁護士が教える税理士損害賠償請求の防ぎ方」(ぎょうせい)